衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第6回:まとめ
2007/08
46. まとめ(その2)
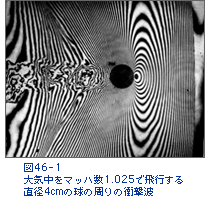 教科書に書かれているのは分かったことばかりで、教科書に書かれていない、しかも、分からない事実の方が多いと思うようになりました。頭の良い人は、教科書にはすべてが書かれていることを信じます。ところが、教科書の記述はほとんど正しいのですが、微妙な部分の解釈には未だ議論が必要です。最近、音の速度近くで移動する球の運動を実験的に検証することに興味を持ちました。弾道飛行装置で球を遷音速で打ち出して、その周り衝撃波を可視化しました(図46-1)。球の前に出来る衝撃波は離脱衝撃波と呼ばれ、衝撃波と球先端との距離を衝撃波離脱距離と言います。球の速度が限りなく音速に近づくと、衝撃波離脱距離は無限大になると教科書に書かれています。 これを「本当かなぁ?」と疑ったのが研究の動機です。球の速度が音速度に漸近すると、離脱衝撃波は不連続的に圧力上昇を伴う構造から、気体の粘性効果が顕著に作用する衝撃波と音波の中間の構造を持つ部分分散波になることが分かりました。だから、球が限りなく音速に近づくと、球の前に現れるのは衝撃波でなく、音波、完全分散波になります。定常流れでは、音速で移動する球の情報は、瞬時に無限遠方にまで伝えられることになります。しかし、現実には、自然は音速の定常流れを「嫌って」います。球は見かけ上音速で移動する瞬間が起こっても、その運動は持続しません。球の情報は有限時間掛かって衝撃波にたどり着き、衝撃波はこの情報に従って構造を変えます。この速度領域で起こる現象は全て時間と共に性質を変え、音速に近い亜音速の球の前にも見かけ上衝撃波が認められ、あたかも亜音速の飛行体の周りにも衝撃波が出来るかの結果も現れます。要するにこの実験をまとめると、音速で飛行する物体近傍の流れは、教科書の記述のようになっていないことが分かります。常識はいつも修正されなければ危険なことに気付きました。
教科書に書かれているのは分かったことばかりで、教科書に書かれていない、しかも、分からない事実の方が多いと思うようになりました。頭の良い人は、教科書にはすべてが書かれていることを信じます。ところが、教科書の記述はほとんど正しいのですが、微妙な部分の解釈には未だ議論が必要です。最近、音の速度近くで移動する球の運動を実験的に検証することに興味を持ちました。弾道飛行装置で球を遷音速で打ち出して、その周り衝撃波を可視化しました(図46-1)。球の前に出来る衝撃波は離脱衝撃波と呼ばれ、衝撃波と球先端との距離を衝撃波離脱距離と言います。球の速度が限りなく音速に近づくと、衝撃波離脱距離は無限大になると教科書に書かれています。 これを「本当かなぁ?」と疑ったのが研究の動機です。球の速度が音速度に漸近すると、離脱衝撃波は不連続的に圧力上昇を伴う構造から、気体の粘性効果が顕著に作用する衝撃波と音波の中間の構造を持つ部分分散波になることが分かりました。だから、球が限りなく音速に近づくと、球の前に現れるのは衝撃波でなく、音波、完全分散波になります。定常流れでは、音速で移動する球の情報は、瞬時に無限遠方にまで伝えられることになります。しかし、現実には、自然は音速の定常流れを「嫌って」います。球は見かけ上音速で移動する瞬間が起こっても、その運動は持続しません。球の情報は有限時間掛かって衝撃波にたどり着き、衝撃波はこの情報に従って構造を変えます。この速度領域で起こる現象は全て時間と共に性質を変え、音速に近い亜音速の球の前にも見かけ上衝撃波が認められ、あたかも亜音速の飛行体の周りにも衝撃波が出来るかの結果も現れます。要するにこの実験をまとめると、音速で飛行する物体近傍の流れは、教科書の記述のようになっていないことが分かります。常識はいつも修正されなければ危険なことに気付きました。
だからといって、研究努力の甲斐もなく分からないことの方が多いから、教科書の記述を信じてはいけないとか、研究が無意味、などと発想を飛躍されても困ります。「努力するから迷う」のは人間で、向上心は人類だけに許された能力で、これは人の先祖が知恵の木の実を食べるよう神様が人間の遺伝子に組み込んだ「陰謀」ではないか、と野狐禅的な悟りに近づいたときは定年退職の年となり、「先生、長い間の研究ご苦労さま。」と丁重に過去を労われ、つい荘子の世界観などと口をすべらせようものなら、「発想も独創的になって…」と、要するに痴呆に近づいたことを優雅に指摘されることになりました。
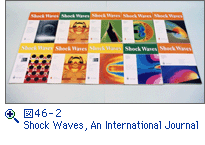 日本の衝撃波研究の機運の高まりは国際的な衝撃波研究の活性化を推進しました。また、国際的な衝撃波研究は最近、学際分野の研究に展開しています。その結果、1990年国際衝撃波雑誌「Shock Waves, An International Journal」(図46-2)が創刊され、2005年には国際衝撃波学会が結成されています。この学会はこの学術誌を研究成果発表の場にして、医学、生物学、医療や地球天体物理学の研究者の参加を得ています。将来、社会科学や人間科学の研究者や研究の話題が加わることが期待されています。
日本の衝撃波研究の機運の高まりは国際的な衝撃波研究の活性化を推進しました。また、国際的な衝撃波研究は最近、学際分野の研究に展開しています。その結果、1990年国際衝撃波雑誌「Shock Waves, An International Journal」(図46-2)が創刊され、2005年には国際衝撃波学会が結成されています。この学会はこの学術誌を研究成果発表の場にして、医学、生物学、医療や地球天体物理学の研究者の参加を得ています。将来、社会科学や人間科学の研究者や研究の話題が加わることが期待されています。
この連載では、化学反応を伴う衝撃波現象や固体中の衝撃波伝播など、幾つかの重要な項目を省略しています。まとめにあたって、幾つか参考文献を記してこの不備を補うことにしました。この連載は、好学の諸氏が衝撃波現象の解明に興味を持っていただくことを目指し、何かのお役に立つことを願って、著者の研究を述べました。
終わりに臨み、この連載を企画し、著者に声を掛けていただいた片山雅英博士、阿部淳博士に謝意を表します。著者の研究には東北大学 流体科学研究所の同僚、学生諸君、東北大学 先進医工学研究機構、東北大学 医学研究科、東北大学 理学研究科の諸先生、また、長年にわたる諸外国の研究仲間の支援を得ています。ここにそのことを述べ各々謝意を表します。また、常に著者の研究に理解と応援を惜しまなかった家族に心から謝意を表します。
- 参考文献
- 国際衝撃波シンポジウム プロシーディングス 1975-2007
- 日本衝撃波シンポジウム論文集 平成2年度~平成17年度
- Shock Waves,an International Journal Vol.1-Vol.16 1990-2007
- ショックウエーヴ 高山和喜 オーム社
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<編集担当より> |
|



