衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第3回:衝撃波の数値模擬
2005/11
11. 数値計算の始まり
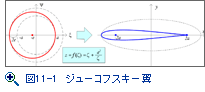 数学は科学の女王といわれ、空気力学は飛行の学の女王と言われた。高校生の時に翼周りの流れを理論的に求めることができることを知って魅せられて、大学では流体力学を勉強しようと決めた。等角写像でジューコフスキー翼(図11-1)の周りの流れを数理解析できることを知り、また、大学院では、与えられた圧力分布を実現する翼形状を、等角写像を駆使して求める解法の一端を学んだ。ジューコフスキー翼は円に等角写像されるが、そのような翼型は円からゆがんだ形になって、そのゆがみの程度を渋面比と呼ぶことを知って、温厚そうな人でも激怒するとひどい人相になり、この術語は人相の変わりの程度を示すのではないかと思った。真面目な翼理論にも笑いがある。
数学は科学の女王といわれ、空気力学は飛行の学の女王と言われた。高校生の時に翼周りの流れを理論的に求めることができることを知って魅せられて、大学では流体力学を勉強しようと決めた。等角写像でジューコフスキー翼(図11-1)の周りの流れを数理解析できることを知り、また、大学院では、与えられた圧力分布を実現する翼形状を、等角写像を駆使して求める解法の一端を学んだ。ジューコフスキー翼は円に等角写像されるが、そのような翼型は円からゆがんだ形になって、そのゆがみの程度を渋面比と呼ぶことを知って、温厚そうな人でも激怒するとひどい人相になり、この術語は人相の変わりの程度を示すのではないかと思った。真面目な翼理論にも笑いがある。
流れの数理解析では物理現象を理解して、複雑な流れを巧妙な近似で解析解を誘導する。境界層近似はその取り扱いの中で最も優れた着想である。しかし、解析解が求められる問題はいままでに解明され尽くして難問のみが残された。フーリエ級数に展開して翼形状を求めるには膨大な手数の数値計算が必要だった。
文部省宇宙科学研究所の小口伯郎先生は最終講義で、昔の東京大学航空研究所では、1講座に5名の助手がいて、20名を越える技官がそろって手回し計算機で数値計算に従事したと話された。アメリカでも同様で、流れの数値解析に大勢の女性が動員されていた。東北大学高速力学研究所では、翼列に最適な翼形状の数値計算に各研究室の手回し計算機の音が廊下中に響いていた。当時は手回し計算機が数値計算の道具で、電動計算機は教授専用で、院生ごときは触れさせて貰えなかった。日本は貧しく、また、電子計算機が現れる前夜の話である。
30年近く前のこと、トロントで開催された国際理論応用力学連合講演会で、当時、境界層の研究で世界的に有名なスチュワートソン教授が「数値計算は科学の女王なりや女中なりや(Is numerical simulation a queen of science or a maid?)」と言う表題で講演した。スーパーコンピューターが普及する直前、複雑な流れの数値模擬がやっと実用になり、複雑な流れ解析にコンピューターが威力を発揮し始めた時だった。数値解析には女王の学にふさわしい論理思考の優雅さが薄れ始め、現象を近似する洞察も不要になって、基礎式を一気に差分近似して計算能力の限りを尽くして解くようになった。だから、数値解析には下働きの女性の腕の太さを感じさせるようになった。なお悪いことに女中と見くびっていたら、腕太の女性はいつの間にか研究者に物理の考察力を忘れさせ、数値計算の結果を真実と思いこませる魔女的な雰囲気を漂わせ始めた。スチュワートソン教授は、そのことに警鐘を鳴らしたかったのだ。
大気中を音速の1.5倍、マッハ数1.5で伝播する衝撃波背後では、圧力は気体分子の平均自由行程の数倍程度の距離で約2.5気圧に上昇する。大気圧空気を構成する窒素や酸素分子の平均自由行程はおおよそ10nmなので、衝撃波は非常に薄く、実用上数学的な不連続面と近似される。また、空気1ccには、おおよそ10の19乗個の気体分子が詰まっている。世界の人口は5×109だから、空気中の気体分子の数は膨大で、特に極低圧でない限り、衝撃波は連続媒体中を伝播する不連続面と考えて良い。
 高速流れを記述する双曲型偏微分方程式を差分近似で数値的に解くとき、衝撃波のような不連続面は特異点になってそこで解は発散する。これを克服するために、1950年代にノイマン(図11-2)とリヒトマイヤーは不連続面の取り扱いに人工粘性項を初めて導入し、見かけ上放物型偏微分方程式の差分近似に置き換えた。その結果、衝撃波や異種気体界面はやや急峻ではあるが連続的に変化し、曲がりなりにも衝撃波の数値計算ができるようになった。数値解析法のその後の発展は、衝撃波を限りなく不連続面として取り扱う理論構成に向けられた。また、1970年代の後半、チョーリンは初めてランダムチョイス法を導入し、ソッドはそれを衝撃波管問題に応用して、初めて衝撃波を不連続面として取り扱うことに成功した。しかし、ランダムチョイス法は衝撃波管流れなど一次元問題に威力を発揮したが、衝撃波の位置が定まらないという曖昧さを含んでいた。その後様々の高速流れの数値解法が開発されたが、いつも衝撃波管流れの数値解析はベンチマークテストの課題に採択された。
高速流れを記述する双曲型偏微分方程式を差分近似で数値的に解くとき、衝撃波のような不連続面は特異点になってそこで解は発散する。これを克服するために、1950年代にノイマン(図11-2)とリヒトマイヤーは不連続面の取り扱いに人工粘性項を初めて導入し、見かけ上放物型偏微分方程式の差分近似に置き換えた。その結果、衝撃波や異種気体界面はやや急峻ではあるが連続的に変化し、曲がりなりにも衝撃波の数値計算ができるようになった。数値解析法のその後の発展は、衝撃波を限りなく不連続面として取り扱う理論構成に向けられた。また、1970年代の後半、チョーリンは初めてランダムチョイス法を導入し、ソッドはそれを衝撃波管問題に応用して、初めて衝撃波を不連続面として取り扱うことに成功した。しかし、ランダムチョイス法は衝撃波管流れなど一次元問題に威力を発揮したが、衝撃波の位置が定まらないという曖昧さを含んでいた。その後様々の高速流れの数値解法が開発されたが、いつも衝撃波管流れの数値解析はベンチマークテストの課題に採択された。
|



