衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第2回:高速流れと衝撃波
2005/10
8. 超音速飛行(その3)
高速飛行では衝撃波の存在を無視した議論はできない。また、高速流体力学は機体周りやエンジン内の流れを解明する要素の学問で、中でも衝撃波現象の解明は重要課題である。一方、流体力学のカリキュラムは一次元定常非粘性流れから始まって、二次元流れ、粘性流れ、三次元、非定常流れと展開し、圧縮性流れに触れるのは、学期の終わり近くになる。従って、三次元圧縮性粘性流れ、まして衝撃波の話など、流体力学の付録の話題になる。「卒業して会社に入って、初めて圧縮性流れを本気で勉強した。」などと豪語する会社の研究者など驚くにはあたらない。「衝撃波の研究をしています。」と自己紹介したら、「君、それは特殊な学問だね。」と言う流体力学の専門家すらいる。人は良く理解していることが一般的で、分からないことは特殊だと信じている。定常流れは、たまたま、式の表示と良く合う絵空事の流れで、特殊の極限である。だから、一次元非粘性定常流れに慣れ親しむと、それ以外の流れ現象は皆特殊に見えて、熱心な学生は、流体力学は底が浅い学問と馬鹿にするようになる。
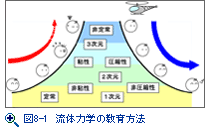 三次元非定常圧縮性粘性流れは流体力学が対象とするすべてを包括する一般的な流れで、教育課程ではこのメニューに衝撃波を含めた非線形が意地悪く現象を支配する様々の流れを見せる必要がある。ドイツの友達と大学の教育について話した。麓から山を登るように段階的に学生を知識の高みに導くのが教育だが、ドイツでは、この教育法で本当に理解する学生は三分の一に過ぎないとのことだった。日本の事情もドイツと同様かもっと悪いと卑下して、もし、学生をヘリコプターで一気に山頂に連れて行って、麓まで駈け下れと命じるような教育法(図8-1)を採用したら、もう少し多くの学生が生き残るのではないかとアナロジーを提案したら、答えてくれなかった。
三次元非定常圧縮性粘性流れは流体力学が対象とするすべてを包括する一般的な流れで、教育課程ではこのメニューに衝撃波を含めた非線形が意地悪く現象を支配する様々の流れを見せる必要がある。ドイツの友達と大学の教育について話した。麓から山を登るように段階的に学生を知識の高みに導くのが教育だが、ドイツでは、この教育法で本当に理解する学生は三分の一に過ぎないとのことだった。日本の事情もドイツと同様かもっと悪いと卑下して、もし、学生をヘリコプターで一気に山頂に連れて行って、麓まで駈け下れと命じるような教育法(図8-1)を採用したら、もう少し多くの学生が生き残るのではないかとアナロジーを提案したら、答えてくれなかった。
時代は変わっている。私が籍を置いた研究室に配属された「頑是無い4年生」が、院生の先輩が奮戦している数値計算や実験の一部を任されて、半年ほど放置しておくと、何かを飲み込んで尤もらしい結果を出し、それなりの物理解釈を述べるようになった。獅子の子の谷落し教育法と言えば体裁が良いが、山の高みで解き放した教育法が今の時代にあっているのかもしれない。だから、非定常の流体力学が基本で、非線形性を理解するために衝撃波現象を題材にするのは適当だったと考えている。
|



