衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第3回:衝撃波の数値模擬
2005/11中旬
15. 衝撃波を目で見る(その1)
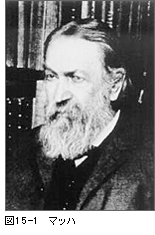 衝撃波を目で見ることは簡単ではない。空気中の衝撃波は毎秒数100mの速度で伝播し、衝撃波背後の密度変化は透明なので、衝撃波を普通の光学撮影法で観測することはできない。しかし、自然界では火山噴火で火口から放出される衝撃波や大規模爆発実験の爆風など、日光の方向と背景の雲の位置など、偶然要素の組み合わせで写真撮影されることがある。いかに高速現象でも、現象から十分離れた観測者は、非常に小さな倍率で記録するので、見かけの速度は微速になり、普通のカメラで観測できる。同様に、毎秒数千kmで動く数万光年も離れた星の動きは、記録画像の倍率が限りなくゼロに近いので、地球上の観測者には静止像となって見える。
衝撃波を目で見ることは簡単ではない。空気中の衝撃波は毎秒数100mの速度で伝播し、衝撃波背後の密度変化は透明なので、衝撃波を普通の光学撮影法で観測することはできない。しかし、自然界では火山噴火で火口から放出される衝撃波や大規模爆発実験の爆風など、日光の方向と背景の雲の位置など、偶然要素の組み合わせで写真撮影されることがある。いかに高速現象でも、現象から十分離れた観測者は、非常に小さな倍率で記録するので、見かけの速度は微速になり、普通のカメラで観測できる。同様に、毎秒数千kmで動く数万光年も離れた星の動きは、記録画像の倍率が限りなくゼロに近いので、地球上の観測者には静止像となって見える。
マッハ(図15-1)は19世紀のオーストリア-ハンガリー二重帝国の物理学者で、プラーハ大学で物理の教授だったとき、プラーハの街を流れるモルダウ河の橋の上から航行する砕氷船を見て、舳先にできる水波から、もし音の速さを超えて動くものがあれば、その先端には丁度砕氷船の舳先の水波のような波が現れるに違いないと思ったと言う。マッハが水面の微小擾乱の伝播速度が水深の平方根に比例する事実を知っていたかどうかは分からないが、底の浅い水路の水波の伝播は衝撃波類似現象なので、マッハの連想は正しかった。マッハは煤を塗ったガラス板の上で二つの電極の同時放電し、発生する球状衝撃波が相互干渉してV字型に煤が剥ぎ取られる部分の出現を見つけた。これは、その形からマッハVと呼ばれたが、1946年代にノイマンは、これは衝撃波異常反射の表れで、マッハ反射と名付けた。
| テプラー(図15-2)が気中放電で発生した球状衝撃波が壁面からの反射する影写真撮影に初めて成功した。放電の球状衝撃波の到達位置に同期させてライデンに溜めた電荷の放電で瞬間光源を構成して、時系列的に衝撃波を感度の低い湿式乾板に低倍率で記録した。また、その画像をスケッチした結果を1868年のパリ万博で展示したと言われている。この万博には、薩摩藩は日本の代表と僭称し、また、徳川家も日本として出品展示した。日本の侍がテプラーの衝撃波反射のスケッチの展示を見たどうかは分からない。侍の語学力の問題でなく、多分このように込み入った理学の話に関心が無く、また、他に見る物が沢山あったのだろう。テプラーのスケッチ(図15-3)は日本の歴史に触れる一瞬があった。 | 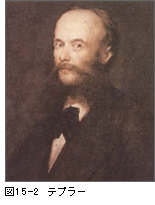 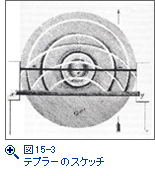 |
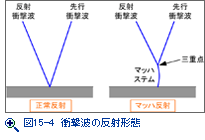 衝撃波が壁から斜めに反射するとき、壁に入射する入射衝撃波が反射点を壁に置いてV字型に反射する形態は光束が鏡から反射する現象を連想させるので、正常反射と呼ぶ。しかし、衝撃波強さと入射角によって、入射衝撃波は壁から離れた点で反射衝撃波につながりその点から壁に垂直に第三の衝撃波が現れるY字型の反射形態をとる。これはマッハ反射と呼ばれ、衝撃波の非線形性の典型的な現れである(図15-4)。テプラーは反射衝撃波形態で正常反射のみを示しマッハ反射を記録しなかった。比較的弱い球状衝撃波のマッハ反射では、衝撃波三重点を特定するのは難しいが、もし、テプラーがマッハ反射の痕跡でも記録に残していたら、現在、マッハ反射と呼ばれている衝撃波の反射形態は、テプラー反射と呼ばれていたかも知れない。テプラーは大発見の長蛇を逸した。
衝撃波が壁から斜めに反射するとき、壁に入射する入射衝撃波が反射点を壁に置いてV字型に反射する形態は光束が鏡から反射する現象を連想させるので、正常反射と呼ぶ。しかし、衝撃波強さと入射角によって、入射衝撃波は壁から離れた点で反射衝撃波につながりその点から壁に垂直に第三の衝撃波が現れるY字型の反射形態をとる。これはマッハ反射と呼ばれ、衝撃波の非線形性の典型的な現れである(図15-4)。テプラーは反射衝撃波形態で正常反射のみを示しマッハ反射を記録しなかった。比較的弱い球状衝撃波のマッハ反射では、衝撃波三重点を特定するのは難しいが、もし、テプラーがマッハ反射の痕跡でも記録に残していたら、現在、マッハ反射と呼ばれている衝撃波の反射形態は、テプラー反射と呼ばれていたかも知れない。テプラーは大発見の長蛇を逸した。
|



