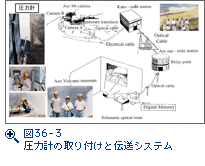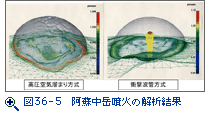衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第5回:衝撃波と地球惑星物理とのつながり
2006/10
36. 噴火の数値模擬(その1)
くぬぎ平で記録できた爆風系の記録から6月19日噴火の爆風のマッハ数を推定できたのに励まされて、この噴火を数値シミュレーションで再現することにした。国土地理院の数値地図から、火山の三次元地形を数値座標に取り込んだ。また、桜島の噴火模擬も試みたが、これはもっとも面倒な作業だった。数値地図が未だなかったので25,000分の1地形図から、余分な記号や表示を手作業で消して投影機に映る等高線を手作業で読み込み、計算機上に三次元の計算メッシュを張り巡らした。スキャナーが普及する以前のことで、手作業には泣きたくなるような時間が掛かった。当時の研究室には現在ケンブリッジ大学航空学科助教授 ホルガーバビンスキー博士が助手で在籍していた。彼の提案で地図の等高線から直接数値座標を構築する作業が始まった。最初、1ヶ月掛かると予定した仕事は難航し、ホルガーが「引き受けるんでなかった。」とぼやき始めたころ完成した。
普賢岳の計算領域は10 km × 10 km、上空方向に4 kmとした。普賢岳の溶岩ドームは日々成長したので、山頂付近の地形は有意に計算格子とは異なるが無視した。噴火のメカニズムはよく分からないが、最初のエネルギー解放をTNT換算で40キロトンを仮定して、二通りの初期状態を想定した。第一は、火口付近に500MPa、2700Kの空気溜まりをおいてこれが瞬間的に解放されるとしたモデルである。第二は、火口直下に全長500m、長さ125 mの高圧室100MPa、2880 Kからなる仮想的な衝撃波管をおき、火口をふさぐ岩石が除去されることを、隔膜破断におきかえて噴火を模擬した。その結果、初期状態の違いで、形成される衝撃波の伝播は少し異なった。また、衝撃波は火山の斜面に沿って伝播する過程で減衰するばかりでなく、局所的な地形変化に対応する斜面傾き角の違いで、マッハ反射や正常反射の形態を示した。その結果は衝撃波背後の圧力分布や減衰の程度に強い影響を与えることが分かった。火山の周辺に精密な圧力計をおいて測定できたら、明らかに局所地形の影響を知ることができる。
 さらに詳細な数値模擬と爆風計計測の準備を進めている間に、普賢岳の噴火は終息した。長い視野で、火山噴火に現れる衝撃波現象を解明することを目標に、阿蘇中岳(図36-2)の噴火による爆風を測定し、数値模擬の爆風圧と比較することにした。阿蘇山の噴火形態は、噴火の段階を追って変わり必ずしも爆発的ではないが、阿蘇中岳は火口のすぐ近くで爆風圧が計測できる日本で唯一の火山である。
さらに詳細な数値模擬と爆風計計測の準備を進めている間に、普賢岳の噴火は終息した。長い視野で、火山噴火に現れる衝撃波現象を解明することを目標に、阿蘇中岳(図36-2)の噴火による爆風を測定し、数値模擬の爆風圧と比較することにした。阿蘇山の噴火形態は、噴火の段階を追って変わり必ずしも爆発的ではないが、阿蘇中岳は火口のすぐ近くで爆風圧が計測できる日本で唯一の火山である。
火口湖の直径は約400mで、100m~150mの切り立った断崖二カ所に厳重な防爆構造のコンクリート製の小屋があり、その中に監視テレビカメラが噴気孔を見下ろす位置に取り付けられ、電源と計測結果を伝送できる光ケーブルが配線されている。自作のやや高感度の圧力計をテレビカメラの横に、火口に対面するように取り付けた。図36-3は圧力計の取り付けと伝送を模式的に示している。計測した信号は光変換して4 km離れた火山博物館に伝送し、パーソナルコンピューターとデジタルメモリーに1ワード5μ秒のサンプリング速度で10秒間の記録し、計測結果は電話回線で東北大学から制御し、取得できる。この記録システムは常時待ち受け状態になっていて、雑音の値を超える微気圧変動の入力で記録が開始される。なお、システムの設営と準備には火山博物館の好意と協力で、1995年から運用が始まった。口の悪い傍観者は「大学の先生が精密計測装置を火山に取り付ければ、どう言う訳か大噴火は起こらないので、火山防災になる。」と言った。事実、まだ大噴火は起こっていない。
 数値地図から阿蘇中岳付近の計算格子を作り、初期条件を仮定して噴火を模擬する準備は整った。図36-4は火口を北から眺めた数値格子で構成した地形を示している。赤の点は圧力計取り付け位置を示す。図36-5は雲仙普賢岳の解析と同様に二通りの初期状態を仮定した場合の解析結果である。実際に噴火が発生した際に爆風計測が成功したら、測定値は地形の効果を含んでいるから、種々、実測値に近い圧力の時間変化を再現するように数値解析の初期条件を設定できれば、この初期条件設定から火道の構造や圧力、温度を推定できる。この研究は始まったばかりで結果はでていない。
数値地図から阿蘇中岳付近の計算格子を作り、初期条件を仮定して噴火を模擬する準備は整った。図36-4は火口を北から眺めた数値格子で構成した地形を示している。赤の点は圧力計取り付け位置を示す。図36-5は雲仙普賢岳の解析と同様に二通りの初期状態を仮定した場合の解析結果である。実際に噴火が発生した際に爆風計測が成功したら、測定値は地形の効果を含んでいるから、種々、実測値に近い圧力の時間変化を再現するように数値解析の初期条件を設定できれば、この初期条件設定から火道の構造や圧力、温度を推定できる。この研究は始まったばかりで結果はでていない。
|