衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第6回:まとめ
2007/08
45. まとめ(その1)
衝撃波は非線形の波動方程式で記述されるか、あるいは、記述されているかもしれない現象です。ところが、流体力学の講義を聴いた人はいつのまにか物理現象は数学的に表現される「べき」と思い込んでしまいます。 しかし、数理モデルで表現できる現象はほんの僅かな特殊な場合で、身のまわりに起こる多くの現象は数学的な記述に収まるどころか混沌としていて、物理モデルが決まらないのが一般的です。情報伝達、株の暴落や高騰が波及する現象、群衆のパニック現象の現れ方などは、波動現象に類似と考えた方がより自然な例が多くあります。多分このように多くの複雑な要素からなる波動現象は、流体力学の保存則とは異なる高次の非線形性を持っているのかもしれません。一方、人間の行動や社会学の現象を数理モデルで説明するのは不可能で、目鼻をつけたら混沌が死んでしまったと言うことになるのかもしれません。にもかかわらず自然界はこのような議論とは無縁に超然と存在し、とりやけもの、微生物はいわゆる力学的保存則に従って動いているけれど、それを意識することなく、まさしく荘子の世界観が成り立っています。
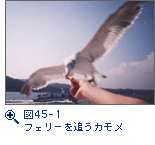 3月に家内が自動車を運転して遠来の親友と九州旅行したときのこと、島原港から熊本新港まで高速フェリーに乗ったとき、沢山のカモメがフェリーを追って飛んできました(図45-1)。カモメは船のすぐ脇を羽ばたくことなく船の速度で移動し、また、船の後流の中にいるカモメはわずかの相対速度の差をゆっくりと羽ばたいて、船の速度に合わせて30kmを越える航路を船を追って飛んでいるのに気がつきました。船を追って飛ぶカモメは昔、青函連絡船での航海でも見ていました。なんと言うことだ!この鳥は境界層を利用し、境界層底流の中を漂っています。大学生のとき、年に何回か青函連絡船の昼間の航海で船を追って飛ぶカモメを見ていたのに、このことに全く気付かなかった。空手や剣道の見切りが肌身にしみこむには、血のにじむ反復練習が必要と聞いています。私が大学の授業で覚えたことが経験として肌身にしみこむのには、少なくとも研究者としての全生涯の時間が掛かったことになりました。
3月に家内が自動車を運転して遠来の親友と九州旅行したときのこと、島原港から熊本新港まで高速フェリーに乗ったとき、沢山のカモメがフェリーを追って飛んできました(図45-1)。カモメは船のすぐ脇を羽ばたくことなく船の速度で移動し、また、船の後流の中にいるカモメはわずかの相対速度の差をゆっくりと羽ばたいて、船の速度に合わせて30kmを越える航路を船を追って飛んでいるのに気がつきました。船を追って飛ぶカモメは昔、青函連絡船での航海でも見ていました。なんと言うことだ!この鳥は境界層を利用し、境界層底流の中を漂っています。大学生のとき、年に何回か青函連絡船の昼間の航海で船を追って飛ぶカモメを見ていたのに、このことに全く気付かなかった。空手や剣道の見切りが肌身にしみこむには、血のにじむ反復練習が必要と聞いています。私が大学の授業で覚えたことが経験として肌身にしみこむのには、少なくとも研究者としての全生涯の時間が掛かったことになりました。
私が本田睦先生に勧められて初めて衝撃波現象を知り、カナダ トロント大学のグラス先生に師事して、衝撃波研究が無限の広がりを持つことを教えられたのは幸運でした。今まで衝撃波現象の解明が航空宇宙工学の基礎を支えることに誇りを持って研究に従事してきました。ところが、いつの間にか衝撃波の学際応用に興味を持ち、特に衝撃波現象を利用して治療装置開発に従事するようになって、極超音速流れや航空宇宙に現れる衝撃波現象など、心躍る研究から遠ざかることになりました。また、医療応用では、力学の大系に無い生命現象の深淵を見てとまどいを感じていました。
生命現象に関わる人は、非線形波動とか数理モデルなどとはほど遠い具象の世界に暮らしていて、イオンの吸引力や反発力で分子構造が変化して窒素分子や酸素分子がその構造の隙間を通過して生体の活動が維持されているとか、遺伝子の解読など、ここには動力学の概念が分け入る隙間があるのだろうかととまどいを感じました。ルネサンス前夜、科学や医療の暗黒時代にスイスの錬金術師で医者だったパラクレススは、人体は自然界と調和して存在し、大宇宙と調和するし小宇宙ではじめて人体をミクロコスモスと呼びました。衝撃波の医療応用は、ちょっぴり詭弁に近いけれどミクロコスモスの研究で、研究者を志したとき最初に抱いた夢を壊すことなく、「連続性を保って」、宇宙の研究に従事していると確信しました。
|



