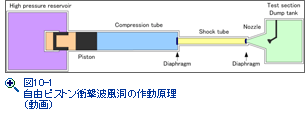衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第2回:高速流れと衝撃波
2005/10
10. 大気圏再突入(その2)
大気圏再突入を地上で再現する最も有効な実験装置に、自由ピストン衝撃波風洞がある。実験では実際の大きさの宇宙機周りの流れを模擬することは出来ないので、バイナリーパラメターと呼ばれる密度と代表長さの積からなる相似パラメーターを一致させて、実験結果から実機周りの流れを推定する。縮尺十分の一モデルで実験すれば、流れ密度は十倍になる。その結果、実験では、流れ密度は十分大きく、また、淀み点温度一万度を実現しなければならない。
自由ピストン衝撃波風洞の作動原理は衝撃波圧縮の極限的な利用である(図10-1)。装置の構造は比較的簡単である。高圧空気を満たした管の末端に重いピストンを置き、ヘリウムを満たし管内に接続している。空気圧でピストンはやや低速で移動してヘリウムを高温高圧に圧縮する。ヘリウムを満たした管はポンプチューブ(または圧縮管)と呼ばれ、隔膜仕切られ空気などの試験気体を満たした衝撃波管に接続している。ポンプチューブ内に一瞬封じ込められた高温高圧ヘリウムが隔膜を破断すると、衝撃波管内に強い衝撃波(SW)を発生できる。衝撃波は衝撃波管末端で反射して、反射衝撃波(RSW)とノズル喉部の間に20MJ/kg、2千気圧を超える貯気槽状態を発生する。貯気槽気体は直ちにノズルを通して膨張、加速され、非常に短時間ではあるがモデルの周りに大気圏再突入状態を再現する。
このとき、バイナリーパラメーター条件を満たすために貯気槽圧力は高く、また温度は数千度に達するので、ノズル喉部の金属は部分的に溶融することがある。もし、衝撃波管端の金属がもしこの条件に1秒間暴露されれば、直ちに溶け始めるが、この極限状態は高々千分の2秒間程度しか持続しないので、壁が溶ける前に実験は終了する。ここでも、高温発生の手段として衝撃波が有効に利用され、断熱圧縮の概念は成り立たないし、2千気圧下で、放電でこの貯気槽条件を得る技術はない。
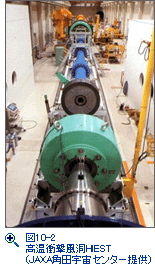 貯気槽条件では、空気は極端な実在気体効果を示し、また、ノズル流れでは解離ないし電離した空気の構成分子は完全に再結合することなく、凍結するのでこの実験法にも不備があるが、他に代わる有効な方法がない。オーストラリア、クイーンスランド大学のストーカー教授は30年間に渡って自由ピストン衝撃波風洞の特性開発に献身し、現在この装置は極超音速流れの実験装置として定着した。日本では、'JAXAの伊藤勝宏博士がストーカー教授の仕事を継承して、経験則を理論的に体系的に明らかにして独創性を発揮し、その理論を基本に高温熱衝撃風洞を設計した。これは全長80mを超え、ノズル出口直径1.5 m 貯気槽エンタルピー25MJ/kgを達成できる世界最大規模のまた最優秀の特性を備えた極超音速実験装置で、現在、高温衝撃風洞HIESTとして角田宇宙推進技術センターで稼働している(図10-2)。この装置の理論予測性能は実験結果とよく一致し、「日本の高速空気力学の研究水準がやっとアメリカやドイツに肩を並べるまでに成長したのではないか」と、開発に関係した研究者を頷かせるものである。
貯気槽条件では、空気は極端な実在気体効果を示し、また、ノズル流れでは解離ないし電離した空気の構成分子は完全に再結合することなく、凍結するのでこの実験法にも不備があるが、他に代わる有効な方法がない。オーストラリア、クイーンスランド大学のストーカー教授は30年間に渡って自由ピストン衝撃波風洞の特性開発に献身し、現在この装置は極超音速流れの実験装置として定着した。日本では、'JAXAの伊藤勝宏博士がストーカー教授の仕事を継承して、経験則を理論的に体系的に明らかにして独創性を発揮し、その理論を基本に高温熱衝撃風洞を設計した。これは全長80mを超え、ノズル出口直径1.5 m 貯気槽エンタルピー25MJ/kgを達成できる世界最大規模のまた最優秀の特性を備えた極超音速実験装置で、現在、高温衝撃風洞HIESTとして角田宇宙推進技術センターで稼働している(図10-2)。この装置の理論予測性能は実験結果とよく一致し、「日本の高速空気力学の研究水準がやっとアメリカやドイツに肩を並べるまでに成長したのではないか」と、開発に関係した研究者を頷かせるものである。
|