衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第2回:高速流れと衝撃波
2005/10
6. 超音速飛行(その1)
| 大昔から人類は空を飛ぶことを憧れた。ギリシャ神話では、オリンポス山にはゼウスが住むとされ、神々が額に汗して山を登るなど信じられなかったのだろう、神々は空を飛んだ。また、神々の住む天空は九つの層状構造を持ち、翼を持つ天使が行き来した。ギリシャや中近東の神話が中国を経て日本に伝わると、天使は翼を捨て、仏教説話にでてくる天女は羽衣をまとって空を飛ぶようになった。
動力飛行は1904年にライト兄弟に始まった。少なくない数の歴史家が、ライト兄弟が初めての動力飛行成功者でないと文献考証している。しかし、ライト兄弟は高等教育を受けることなく、独学で小型の風洞を作り、実験で様々の形状の翼に働く力を計測して飛行機設計に必要な翼形状を最適化した。また、プロペラの理論と経験から飛行安定の理論を構築した上で、発明工夫を基礎に動力飛行機ライトフライヤー(図6-1)を作り、初飛行に成功した。これは後世の科学技術史の評価に耐える快挙で、誠実な研究の当然の成果である。また、ライト兄弟の動力飛行成功の直前に、ペンシルバニア州立大学のラングレー教授は国費の援助を得て動力飛行機エアロドローム(図6-2)を製作し、ポトマック河でボートからの初飛行に失敗している。動力飛行成功の機運は整っていた。 ライト兄弟の研究開発の過程は克明に記録され、これは今日の飛行機設計の基本とほとんど変わらない。だから、アメリカ人はライト兄弟の業績を誇り、NASAはその歴史の継承者と自負し、ラングレー教授はNASAラングレー研究所に名を留めている。 ライト兄弟仕様の飛行機はアメリカ陸軍に採用され、その後多くの変遷を経て、飛行機はより速くより遠くに飛ぶことを目指し改良進化した。第二次世界大戦はプロペラ飛行最後の栄光の時代だった、日本もこの時代に応分の貢献を果たした。飛行機の設計者は大出力のエンジンを搭載して出力をあげ、プロペラ回転数を高めてもプロペラ先端は超音速になり衝撃波が発生し、飛行速度に上限があることを知った。 1930年代の後半、ドイツとイギリスでそれぞれ独立にジェットエンジンが発明された。ドイツのメッサーシュミット262(図6-3)は初めて実用化されたジェット機だった。日本はこれを取り入れようと願い、紆余曲折あってやっと一枚の数字も材料指定もない総組み立て線図を入手した。これから実機をつくる仕事は模倣をというよりは創造に近く、東北大学は「ネ20」と呼ばれたエンジンの設計を担当し、当時高速力学研究所と呼ばれた現在の流体科学研究所は、圧縮機の翼列流れの解析に貢献した。国を挙げての努力の甲斐あって実機は完成し、橘花(図6-4)と名付けられ、終戦の一週間前に初飛行に成功した。 |
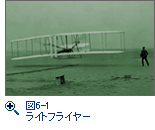 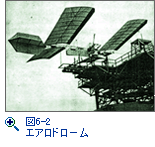 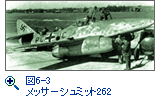  |
|



