衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第5回:衝撃波と地球惑星物理とのつながり
2006/10
33. 水蒸気爆発(その1)
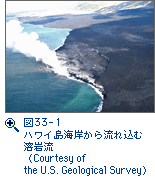 溶岩や溶融金属塊などを水に投入すると高温物体に接した水は瞬間的に蒸発し、高温物体は水蒸気膜で覆われる。水蒸気膜は厚くなり大変形する一方で、局所的に薄くなって高温物体が直接水に接する状態が出現し、高温物体は爆発的に微粒化され、いわゆる水蒸気爆発が起こる。製鉄所や鋳物工場など溶融金属を取り扱う産業では、高温物体を水に投棄するなどの工程の間違いで、水蒸気爆発が起こり、それは重大な産業災害につながることがある。しかし、高温物体が水と接すれば必ず水蒸気爆発が起こるとは限らない。ハワイ島キラウエア火山の噴火では、溶岩の粘性係数が低く、噴出した溶岩は水のように斜面を毎秒数メートルで流れ下って海に注ぎ込む(図33-1)。流れ込んだ溶岩に接した海水は瞬時に沸騰して水蒸気を上げるのみで、壮観だが大規模な水蒸気爆発は観察されない。
溶岩や溶融金属塊などを水に投入すると高温物体に接した水は瞬間的に蒸発し、高温物体は水蒸気膜で覆われる。水蒸気膜は厚くなり大変形する一方で、局所的に薄くなって高温物体が直接水に接する状態が出現し、高温物体は爆発的に微粒化され、いわゆる水蒸気爆発が起こる。製鉄所や鋳物工場など溶融金属を取り扱う産業では、高温物体を水に投棄するなどの工程の間違いで、水蒸気爆発が起こり、それは重大な産業災害につながることがある。しかし、高温物体が水と接すれば必ず水蒸気爆発が起こるとは限らない。ハワイ島キラウエア火山の噴火では、溶岩の粘性係数が低く、噴出した溶岩は水のように斜面を毎秒数メートルで流れ下って海に注ぎ込む(図33-1)。流れ込んだ溶岩に接した海水は瞬時に沸騰して水蒸気を上げるのみで、壮観だが大規模な水蒸気爆発は観察されない。
 1979年、スリーマイルアイランドの原子力発電所(図33-2)で炉心冷却の制御に失敗して炉心の一部が熔解し放射性物質を排出した。1986年、チェルノブイリ原子炉(図33-3)で、原子炉緊急遮断の訓練中に、炉心冷却水循環系に思わぬ不具合が発生し、冷却水の供給が遮断されて炉心熔解が始まった。その結果、崩壊した炉心は周辺材料を溶かし、内部に蓄積した放射性物質と高温気体は高圧となり、原子炉を収容する建物を大破して大気中に噴出した。放射性微粒子は飛散して東ヨーロッパと北欧諸国を巻き込んだ大規模環境汚染を引き起こした。これを契機に、原子炉の炉心溶解の機序解明と有効な対策確立を目指す水蒸気爆発機序解明の研究が世界的な規模で始まった。
1979年、スリーマイルアイランドの原子力発電所(図33-2)で炉心冷却の制御に失敗して炉心の一部が熔解し放射性物質を排出した。1986年、チェルノブイリ原子炉(図33-3)で、原子炉緊急遮断の訓練中に、炉心冷却水循環系に思わぬ不具合が発生し、冷却水の供給が遮断されて炉心熔解が始まった。その結果、崩壊した炉心は周辺材料を溶かし、内部に蓄積した放射性物質と高温気体は高圧となり、原子炉を収容する建物を大破して大気中に噴出した。放射性微粒子は飛散して東ヨーロッパと北欧諸国を巻き込んだ大規模環境汚染を引き起こした。これを契機に、原子炉の炉心溶解の機序解明と有効な対策確立を目指す水蒸気爆発機序解明の研究が世界的な規模で始まった。
 1988年、アメリカ、サンディア国立研究所に滞在中の日本原子力研究所の研究員から、どのような経緯で知ったか分からないが、東北大学で体外衝撃波結石破砕術装置の開発に用いた水中衝撃波収束用の短径150mm半切回転楕円体をサンディア研究所で使えないかとの依頼があった。了解して、半切回転楕円体を発送後、実験視察の要請があったので、やや面倒な手続きの後で当研究所を初めて訪問した。水中に溶融鋼を投下して水蒸気爆発を再現模擬する実験が計画されていた。保安や周囲への騒音問題など考える必要すらない砂漠の広大な敷地に、装置ばかりでなく大がかりな準備が進行中だった。予備実験で溶融鋼を水中に落下させたが、溶融鋼は微細化せず水蒸気爆発も起こらなかったので、落下する溶融鋼塊が計測予定位置に到達したときに同期して、標的物体に衝撃波を収束させて強制的に微細化させ、水蒸気爆発を誘起する目的だった。残念ながらこの実験には立ち会えなかったが、後に微細化成功の知らせを聞いた。
1988年、アメリカ、サンディア国立研究所に滞在中の日本原子力研究所の研究員から、どのような経緯で知ったか分からないが、東北大学で体外衝撃波結石破砕術装置の開発に用いた水中衝撃波収束用の短径150mm半切回転楕円体をサンディア研究所で使えないかとの依頼があった。了解して、半切回転楕円体を発送後、実験視察の要請があったので、やや面倒な手続きの後で当研究所を初めて訪問した。水中に溶融鋼を投下して水蒸気爆発を再現模擬する実験が計画されていた。保安や周囲への騒音問題など考える必要すらない砂漠の広大な敷地に、装置ばかりでなく大がかりな準備が進行中だった。予備実験で溶融鋼を水中に落下させたが、溶融鋼は微細化せず水蒸気爆発も起こらなかったので、落下する溶融鋼塊が計測予定位置に到達したときに同期して、標的物体に衝撃波を収束させて強制的に微細化させ、水蒸気爆発を誘起する目的だった。残念ながらこの実験には立ち会えなかったが、後に微細化成功の知らせを聞いた。
従来、水蒸気爆発の模擬実験には、比較的低融点で水と接触しても化学反応を起こさない錫が使われた。溶融錫を水に投下してその水中挙動を可視化、高速撮影した。投下された複雑な表面形状の溶融錫は水に接触して、凹凸の水蒸気膜に覆われる。溶融錫を覆う水蒸気膜は、時間とともに厚くなるが、部分的に薄くなって溶融錫と水が直接接触する瞬間、接触した水は再び爆発的に蒸発し、溶融錫塊は分裂する。この分裂の機序解明が重要な研究課題である。
一方、従来水蒸気爆発の計測に使われた高速撮影速度は、衝撃波研究に使われる高速カメラの撮影速度に比べ遅く、水中落下の瞬間に発生する圧縮波や水中衝撃波の可視化を目指すものでなかった。高温物体を投下したとき圧力波が発生するが、有限の大きさの試験槽では波は伝播して壁から反射し水蒸気膜に入射する。直径1mの実験槽では、壁から反射した波は約0.7msで溶融錫に到達し、この圧力変動に反応して水蒸気膜は変形する。
水蒸気爆発の機序解明に、衝撃波研究など他分野の研究手法を介入させる余地はなかったが、水中爆発とキャビテーション気泡の干渉を取り扱った経験を水蒸気爆発の解明に結びつけようとして、行き詰まりを感じた。しかし、毛語録に「自分のやり方で戦争をする」と言う記述を見て、この意味するところは政治的だが、研究の心構えに繋がるところもあり、最も得意とする技術や経験を生かして問題解明に迫ると読み替えた。だから、非定常波動や衝撃波の切り口から水蒸気爆発現象を見直すことも有理である。
|



