衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第2回:高速流れと衝撃波
2005/10
7. 超音速飛行(その2)
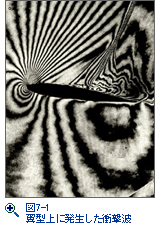 1950年代になって、ロケットエンジンを搭載した超音速機の超音速飛行が成功した。ジェット機での超音速飛行は悲劇的だった。亜音速から超音速に移行するとき機体周りに衝撃波が現れて(図7-1)、機体に働く力と作用位置が変わるので、開発当初、試作機はよく墜落した。人々は空には音の壁があって、超音速飛行を阻んでいるのではないかとさえ言った。世界が超音速飛行に移行し、アメリカとソ連が弾道ミサイルの研究を推進しているとき、日本とドイツの飛行の学問は禁止された。この事実は日本の航空工学、高速空気力学研究に大きな負い目を負わせた。
1950年代になって、ロケットエンジンを搭載した超音速機の超音速飛行が成功した。ジェット機での超音速飛行は悲劇的だった。亜音速から超音速に移行するとき機体周りに衝撃波が現れて(図7-1)、機体に働く力と作用位置が変わるので、開発当初、試作機はよく墜落した。人々は空には音の壁があって、超音速飛行を阻んでいるのではないかとさえ言った。世界が超音速飛行に移行し、アメリカとソ連が弾道ミサイルの研究を推進しているとき、日本とドイツの飛行の学問は禁止された。この事実は日本の航空工学、高速空気力学研究に大きな負い目を負わせた。
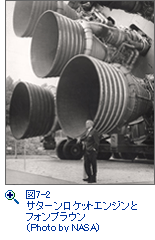 ドイツの航空工学は日本と同様停滞したが、事情は少し違っていた。ミュンヘンのドイツ博物館の展示物の目玉はロケット開発の歴史である。ドイツ人は、ロケット技術発祥の地、ロケット開発の先駆者としての国の誇りを胸に秘めている。
ドイツの航空工学は日本と同様停滞したが、事情は少し違っていた。ミュンヘンのドイツ博物館の展示物の目玉はロケット開発の歴史である。ドイツ人は、ロケット技術発祥の地、ロケット開発の先駆者としての国の誇りを胸に秘めている。
また、フォン ブラウン(図7-2)始めドイツのロケット研究者達は、ロケット開発の目標を有人宇宙飛行と考え、戦争に勝つ手段とは見なしていなかった。空を飛び月に行くのは人類の自然な願望で、宇宙利用を経済活動に限る日本の宇宙開発の動機とは異なり、意気込みと夢を感じさせる。しかし、最近発表された日本の宇宙開発長期計画に将来の有人宇宙飛行が明記されているのは非常に立派な決断で、科学技術を志す若者に夢を持たすものである。
良識を持って自由意志で行った研究や技術開発とそれを利用する第三者の行為とは区別さるべきで、歴史の評価に任せるべき議論であるが、V2ロケットの開発と運用は、後のアメリカのアポロ計画の縮図を感じさせた。最近、ロケット開発の視野から、当時のドイツの高速空気力学の研究事情を綴った「ペーネミュンデの思いで」と言う本を読んだ。ドイツから多くのロケット研究者がソ連とアメリカに連行され、現在の宇宙技術二大国の基礎を築いた事情が良く書かれている。驚いたことに、この本によると戦争前のドイツには、アメリカに負けない規模の超音速風洞があり、また、マッハ数7の極超音速風洞の建設計画があった。
この本を通して、ドイツには、研究技術の伝統を将来に伝えようとの意図を感じた。戦争前の日本にも、ドイツには比較できないが超音速風洞があり、装置は今も防衛庁技術本部第一研究所にある。しかし、昔、稼働した国内研究機関の高速流れ実験装置の記録や資料が、現在、消去されずに残って居るのだろうか。
音の壁を乗り越えて超音速飛行が実現し、さらに、マッハ数2、3の飛行を目指したとき、衝撃波背後の空気温度上昇が無視できない問題となり、人類は熱の壁に立ち向かうことになった。ここに、マッハ数とは飛行速度と音速の比で定義され、音波はマッハ数1の波になる。
 高速飛行に起因する温度上昇は空力加熱と呼ばれ、衝撃波が関与する高速飛行の大きな課題である。断熱圧縮では、空気の温度は圧力の0.3乗に比例して上昇するが、強い衝撃波では、温度はほぼ圧力に比例して上昇するので、衝撃波は高温発生の有効な手段となる。1960年代の半ば、東京-ニューヨーク間を、マッハ数5で飛行して5、6時間で結ぶ極超音速飛行プロジェクトが立ち上がり、ボーイング社とロッキード社ではそれぞれの技術でエンジンを試作した。航空宇宙学会の年会でアメリカ人講師が夢の極超音速飛行を特別講演し、胸躍る思いで聴講した。機体はチタン合金製で、空力加熱の熱膨張を考慮して、地上ではしわだらけの表面だった。後日、マッハ数3で飛行するSR-71(図7-3)を至近距離で見る機会があった。その表面はしわだらけだった。
高速飛行に起因する温度上昇は空力加熱と呼ばれ、衝撃波が関与する高速飛行の大きな課題である。断熱圧縮では、空気の温度は圧力の0.3乗に比例して上昇するが、強い衝撃波では、温度はほぼ圧力に比例して上昇するので、衝撃波は高温発生の有効な手段となる。1960年代の半ば、東京-ニューヨーク間を、マッハ数5で飛行して5、6時間で結ぶ極超音速飛行プロジェクトが立ち上がり、ボーイング社とロッキード社ではそれぞれの技術でエンジンを試作した。航空宇宙学会の年会でアメリカ人講師が夢の極超音速飛行を特別講演し、胸躍る思いで聴講した。機体はチタン合金製で、空力加熱の熱膨張を考慮して、地上ではしわだらけの表面だった。後日、マッハ数3で飛行するSR-71(図7-3)を至近距離で見る機会があった。その表面はしわだらけだった。
|



