衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第5回:衝撃波と地球惑星物理とのつながり
2006/10
34. 水蒸気爆発(その2)
体外衝撃波結石破砕術には結石破砕の副作用として、僅かに生体も損傷した。これは基本的には衝撃波と気泡が干渉して気泡の変形収縮が起こり、高速水ジェットが発生して、生体組織に貫入する現象に起因する。要するに、衝撃波/気泡干渉での水ジェット発生は、気泡の曲率半径が有限だから起こる。平面水中衝撃波が平面の気液界面に正面衝突する現象、あるいは気体中で平面衝撃波が水面に衝突する現象には、解析解が知られている。平面水中衝撃波の衝突では、衝撃波は気中に透過して気液界面を気中に押し上げ、水はもはや非圧縮性媒体ではなくて、また、含有気体の影響を受ける「実在液体」として圧縮、膨張するので、気液界面直下の圧力は減少して大きな引っ張り力が発生し、言い換えると、スポーリング効果の表れとして、反射波は膨張波になり、気液界面直下にはキャビテーション気泡が発生する。
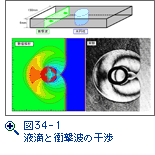 一方、空気中で液滴に衝撃波が作用するとき、あるいは水中で気泡に衝撃波が作用するときには、この一次元理論は適用できない。現象は非定常で複雑になる。一様流れで、衝撃波の負荷で液滴が時間とともに変形し、最後に微粒化する現象は、内燃機関の噴霧燃焼の素過程解明にも関連して、多くの実験がある。我々はこの素過程を実験室で再現し模擬するために、衝撃波管内に液滴を滴下あるいは蜘蛛の巣の糸など細いひもに貼り付けておき、衝撃波を作用させ、衝撃波と高速気流で液滴が変形、微粒化する過程をホログラフィー干渉計で定量的可視化を目指した(図34-1)。
一方、空気中で液滴に衝撃波が作用するとき、あるいは水中で気泡に衝撃波が作用するときには、この一次元理論は適用できない。現象は非定常で複雑になる。一様流れで、衝撃波の負荷で液滴が時間とともに変形し、最後に微粒化する現象は、内燃機関の噴霧燃焼の素過程解明にも関連して、多くの実験がある。我々はこの素過程を実験室で再現し模擬するために、衝撃波管内に液滴を滴下あるいは蜘蛛の巣の糸など細いひもに貼り付けておき、衝撃波を作用させ、衝撃波と高速気流で液滴が変形、微粒化する過程をホログラフィー干渉計で定量的可視化を目指した(図34-1)。
この課題を担当したイスラエルの博士課程院生が実験と数値計算結果を微粒化研究会で発表した。発表に対して「衝撃波管内の流れでの液滴崩壊は非定常現象で、我々の風洞流れでの微粒化は定常流れの実験だから、衝撃波管実験は異なる微粒化である。」と底意地の悪い質問があったと院生は情けない顔で報告に来た。答えて言った、「今度同じ質問を受けたらこう答えよ。衝撃波管に液滴を固定して、衝撃波を入射して最初の波動干渉による非定常過程を経験した後、衝撃波背後の定常流れを作用させる実験と、定常流れと思いこんでいる風洞流れに液滴を導入する非定常過程を経過した後で液滴が定常流れにさらされる実験との間のどこに違いがあるのか、と。それよりも、風洞流れを定常と見なすのは単なる思いこみで、厳密に言えば定常流れは時間に無関係な流れを意味するから、定常流れ風洞は世界の始まりから運転されていたことになる」と。この“定常とは世界の始まりから続く流れ”というのは大げさだが、定常流れは架空現象で、現実の流れには乱流があり、始めと終わりがある。液滴を定常流れに導入した瞬間に流れは非定常となり時間が支配する。動力学の面白さは時間に支配される現象の解明で、時間変化のない現象はきわめて特殊である。
だから、水蒸気爆発の解釈も同様で、凸の水蒸気界面に衝撃波が作用すると、衝撃波/気泡の干渉と類似して、界面は収縮変形して流れを誘起し、曲率最大点近傍で流れは淀んで圧力最大となり、最大圧力は気泡を変形させて、その点は押されて凹み、凹みはさらに加速的に変形してジェットを形成する。この水ジェットが高速で溶融物体に貫入、直接接触を誘起して爆発的な沸騰が起こる。その結果、局所的に衝撃波が発生し、隣り合う水蒸気界面に作用する。これらの過程は連鎖反応的に進行する。連鎖反応の伝播速度は水の音速程度と推定されるから、溶融物体は瞬時に爆発的に破砕される。アジ演説で暴動が起こったり、風説でトイレットペーパー買い占めのパニックが起こった過程を連想させる。
一方、液体に接した加熱面から、単位面積、単位時間当たりどのくらいの熱量が伝達できるかということは、伝熱工学の研究課題である。伝熱量が大きく極限に達すると、蒸気膜と伝熱面の接触が支配的になり、マグマ水蒸気爆発あるいは原子炉溶解で起こった状態が現れる。そこでは、気液二相媒体中での衝撃波の挙動を無視した議論はできない。
ハワイ火山の場合、海に流れ込む溶岩のエネルギー量は膨大だが、溶岩は空間をゆっくり移動するので、単位面積、単位時間当たりの水に伝達される熱エネルギーの量は大きくない。一方、チタンとグラファイト粉末を等量混合し圧縮成型した塊を炭酸ガスレーザーで加熱すると、高温自己発熱反応(self-sustained high-temperature synthesis SHS反応)が起こる。チタン・グラファイト塊は白く輝き、大気圧下で容易に3000Kに達する。自己発熱反応を起こしている直径約10mmのチタン・グラファイト塊を100リットルの水槽に落したところ、水蒸気爆発が起こり、チタン・グラファイト塊は微細破片となった。この実験では単位面積、単位時間当たりのエネルギー伝達量が非常に大きいので水蒸気爆発が起こった。経験的に、水蒸気爆発が発生する領域と境界はエネルギー伝達率に支配されていると考えている。
水蒸気爆発は産業災害に現れるばかりでなく、火山噴火にも現れる。局所的な地震などでマグマ溜まりの壁が崩壊するとマグマ溜まりの圧力は短時間で減少し、水や炭酸ガスなどマグマ中に過飽和に溶融している揮発性物質が発泡する。その結果、マグマ密度は減少しマグマは地表に上昇し始める。マグマが上昇中に地下水帯に遭遇すると、マグマは水に直接接触して水蒸気爆発に類似の現象が起こる。これはマグマ水蒸気爆発と呼ばれる噴火の機序で大規模噴火につながることが知られている。
人為的な原因で起こる水蒸気爆発とマグマ水蒸気爆発の類似性に注目して原子核工学者と火山学者の連携で、文部省科学研究費重点領域研究「水蒸気爆発の解明」が発足した。この3年間の研究では、現象の規模に無関係に水蒸気爆発の機序を記述できる普遍的な相似パラメーターは特定できなかった。また、噴火で現れる水蒸気爆発と人為的な原因で起こる水蒸気爆発は異なる現象との結論に達した。しかし、学際領域研究が進み、衝撃波研究者を含め関連他分野の研究とのつながりが無視できないことが分かったのは収穫であった。
|



