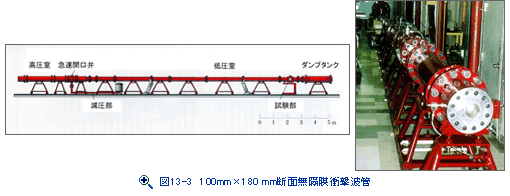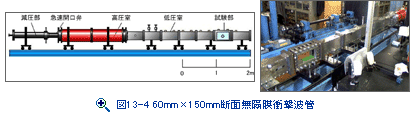衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第3回:衝撃波の数値模擬
2005/11
13. 衝撃波管(その2)
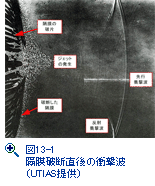 高圧気体と低圧室気体の差圧にもよるが、隔膜が破断すると、殆ど瞬間的に湾曲した衝撃波が発生する。日本航空のジャンボ機が機体後部の隔壁の破断で制御の油圧系を破損して墜落した事故で、湾曲した隔壁破断の模擬実験をしたことがある。直ちに湾曲した衝撃波が発生し伝播した。その衝撃波の一部は垂直尾翼付け根の点検穴から断面積が漸近的に狭まる構造の垂直尾翼を駆け上がり、収束して高圧を発生し、その圧力で方向舵を吹っ飛ばした。事故の後、多くの人が、衝撃波は直ぐには形成されないから、その作用で方向舵は壊れるはずがないと主張し、その理由に衝撃波管の衝撃波形成距離を引用した。湾曲した衝撃波は破膜後直ちに発生するのだ(図13-1)。事故調査委員会は衝撃波の作用には殆ど言及していないが、事故の責任を問われたボーイング社は直ちに垂直尾翼の付け根に開いた点検穴を塞いだ。また、生存者の証言では、隔壁が破れた瞬間客室に霧が発生している。これは客室圧力が減圧されても機外圧力よりも高いので、客室は衝撃波管の高圧室に等価となり、霧の発生は高圧室中を伝播した膨張波の断熱膨張による温度降下の結果である。
高圧気体と低圧室気体の差圧にもよるが、隔膜が破断すると、殆ど瞬間的に湾曲した衝撃波が発生する。日本航空のジャンボ機が機体後部の隔壁の破断で制御の油圧系を破損して墜落した事故で、湾曲した隔壁破断の模擬実験をしたことがある。直ちに湾曲した衝撃波が発生し伝播した。その衝撃波の一部は垂直尾翼付け根の点検穴から断面積が漸近的に狭まる構造の垂直尾翼を駆け上がり、収束して高圧を発生し、その圧力で方向舵を吹っ飛ばした。事故の後、多くの人が、衝撃波は直ぐには形成されないから、その作用で方向舵は壊れるはずがないと主張し、その理由に衝撃波管の衝撃波形成距離を引用した。湾曲した衝撃波は破膜後直ちに発生するのだ(図13-1)。事故調査委員会は衝撃波の作用には殆ど言及していないが、事故の責任を問われたボーイング社は直ちに垂直尾翼の付け根に開いた点検穴を塞いだ。また、生存者の証言では、隔壁が破れた瞬間客室に霧が発生している。これは客室圧力が減圧されても機外圧力よりも高いので、客室は衝撃波管の高圧室に等価となり、霧の発生は高圧室中を伝播した膨張波の断熱膨張による温度降下の結果である。
 衝撃波管実験では毎回隔膜を取り替えなければならない。また、破断した隔膜の開口部面積は衝撃波管断面積より小さいので、隔膜開口部は一種のオリフィスとなり、実験の度に僅かに変化する。だから、全く同じ条件で衝撃波を発生しても、その衝撃波マッハ数は良くて1%、漫然と準備すれば5%程度ばらつく。大きな衝撃波管では隔膜交換は肉体労働になる。1994年、トロント大学のグラス教授が長年愛用したHypervelocity Shock Tubeと直径230mmのマッハツェンダー干渉計一式は、グラス教授引退を機会に東北大学との国際共同研究を推進するために、流体科学研究所に寄贈された(図13-2)。これは1960年代後半に設計され1970年代の始めに稼働開始し、アポロ計画の基礎研究を支え、大学が保有できる最高の特性を有する衝撃波管だった。この衝撃波管の断面は100mm×180mmで、全長約20m、高張力鋼でできていて内面はクロームメッキされ、容易にマッハ数15を達成できる。当初、この衝撃波管には厚いステンレス板に十字溝を切った隔膜を使っていたので、その取り替えは簡単でなく、日に2回の実験ができた。
衝撃波管実験では毎回隔膜を取り替えなければならない。また、破断した隔膜の開口部面積は衝撃波管断面積より小さいので、隔膜開口部は一種のオリフィスとなり、実験の度に僅かに変化する。だから、全く同じ条件で衝撃波を発生しても、その衝撃波マッハ数は良くて1%、漫然と準備すれば5%程度ばらつく。大きな衝撃波管では隔膜交換は肉体労働になる。1994年、トロント大学のグラス教授が長年愛用したHypervelocity Shock Tubeと直径230mmのマッハツェンダー干渉計一式は、グラス教授引退を機会に東北大学との国際共同研究を推進するために、流体科学研究所に寄贈された(図13-2)。これは1960年代後半に設計され1970年代の始めに稼働開始し、アポロ計画の基礎研究を支え、大学が保有できる最高の特性を有する衝撃波管だった。この衝撃波管の断面は100mm×180mmで、全長約20m、高張力鋼でできていて内面はクロームメッキされ、容易にマッハ数15を達成できる。当初、この衝撃波管には厚いステンレス板に十字溝を切った隔膜を使っていたので、その取り替えは簡単でなく、日に2回の実験ができた。
東北大学に移設されて、我々は種々の改良を施した(図13-3)。まず、高圧室を内径155mm、外径355mm、長さ5mの内面にクロームメッキした国産の高張力鋼管に置き換え、測定部をステンレス鋼の180mm×1,100 mm視野に拡大し、強い衝撃波実験で、衝撃波、実在気体の非平衡領域と接触領域全てを1枚のフィルムに記録することを目指した。特に大きな改良は、隔膜破断方式を廃止して、高圧室に対面する軽量ピストンで高圧気体を封じ、ピストンを急に後退させて高圧気体を低圧室に流入させる、無隔膜衝撃波管にしたことだった。ピストンを制御して50mmの距離を急速後退させることは比較的容易だったが、さらに短い距離で減速静止させることは難しい設計が必要だった。また、300mm口径のターボ分子ポンプを排気系に導入したので、実験の繰り返し時間は20分程度になり、衝撃波マッハ数のばらつきは、空気を試験気体にマッハ数1.5~5.0の範囲で、0.3%以内になった。この改良で実験精度は極端に良くなった。隔膜破断方式で起こる、大小の隔膜破片が飛び散って測定部に取り付けたモデルに衝突してその表面をこすって破損することもなくなり、また、実験毎に隔膜部を開き、隔膜交換や衝撃波管内面掃除もなくなった。特に、実在気体効果の研究では、試験気体の純度が重要になる。衝撃波管壁を大気に曝すと大気中の水蒸気が管壁に吸着して実験の精度が保証されない。衝撃波管内面を大気開放なしに実験ができるので、衝撃波管の内面汚染も低減されたばかりでない、毒性気体を試験気体にする実験も可能になった。
また、弱い衝撃波を再現性良く発生することを目指して、補助高圧で張り出したネオプレンゴム膜で高圧室と低圧室とを仕切り、補助高圧を急速に排気してゴム膜をしぼませて、隔膜破断と同様の効果を得る方式の60mm×150mm無隔膜衝撃波管を設置している。この衝撃波管は、空気を試験気体にマッハ数1.1~2.0の範囲で、マッハ数のばらつきは0.2%以下を達成できた。この装置の設計製作は、院生の楊基明君(現在 中国科学技術大学教授)と流体科学研究所工場の技官諸氏の努力の結果である。
|