衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第4回:衝撃波の医療応用
2006/04
21. 水中衝撃波とキャビテーション(その1)
 東北大学高速力学研究所は1990年に流体科学研究所(図21-1)に改組され、附属施設衝撃波工学研究センターを加えた。高速力学という名称は高速水流を意味し、改組を機会に高速空気力学の研究を充実させた。研究所の創設者、沼知福三郎教授は1943年キャビテーション現象の解明と水力機械の小型化と高性能化を目指して、高速力学研究所を設置した。この時代、ポンプや発電用タービン翼周りの流れの解明は、航空機の研究と並んで流体力学研究のもう一つのハイライトだった。沼知先生は1931年から文部省の在外研究員として三年間ドイツに留学し、ゲッチンゲンのマックスプランク流体研究所に滞在してプラントル教授の薫陶を受けた。キャビテーション現象の研究視察のためにドイツ各地の大学を訪問し、キール大学で回流水槽測定部の気泡発生を制御できなくなっているのを見て、水中の空気含有率がキャビテーション現象を支配することに気付いたと言う。この着想を胸に秘め帰国して、水中空気含有率測定の簡便で正確な装置を設計製作した。空気含有率の計測は知られていたが複雑で実用的でなかった。しかし、沼知先生が提唱した空気含有率測定は簡単で実用的だった。この装置は流体科学研究所二号館のロビーに展示されている。
東北大学高速力学研究所は1990年に流体科学研究所(図21-1)に改組され、附属施設衝撃波工学研究センターを加えた。高速力学という名称は高速水流を意味し、改組を機会に高速空気力学の研究を充実させた。研究所の創設者、沼知福三郎教授は1943年キャビテーション現象の解明と水力機械の小型化と高性能化を目指して、高速力学研究所を設置した。この時代、ポンプや発電用タービン翼周りの流れの解明は、航空機の研究と並んで流体力学研究のもう一つのハイライトだった。沼知先生は1931年から文部省の在外研究員として三年間ドイツに留学し、ゲッチンゲンのマックスプランク流体研究所に滞在してプラントル教授の薫陶を受けた。キャビテーション現象の研究視察のためにドイツ各地の大学を訪問し、キール大学で回流水槽測定部の気泡発生を制御できなくなっているのを見て、水中の空気含有率がキャビテーション現象を支配することに気付いたと言う。この着想を胸に秘め帰国して、水中空気含有率測定の簡便で正確な装置を設計製作した。空気含有率の計測は知られていたが複雑で実用的でなかった。しかし、沼知先生が提唱した空気含有率測定は簡単で実用的だった。この装置は流体科学研究所二号館のロビーに展示されている。
高速力学研究で学んだ院生は専門に関係なく「門前の小僧習わぬ経を読む」の譬えのようにキャビテーション現象を覚えた。だから、1970年、高速力学研究所の本田 睦教授の指導で衝撃波管の実験研究に従事したとき、衝撃波管で水中衝撃波の研究ができないかと考えた。気体中の衝撃波が液面に沿って伝播すれば、液体中にも圧縮波ないし衝撃波が伝播する。まず、気液界面の挙動に興味を持ち、気中の衝撃波のマッハ数とは別に、気体と液体の粘性係数と密度の積の比が現象を支配することに気付いた。この比が1になれば気液界面の違いは僅かになるので、高粘度、高密度気体と低粘度、低密度粘性液体の組み合わせが望ましい。そこで、各種気体と液体の組み合わせの中で、塩素中を伝播する衝撃波がアセトン液面を伝播する場合を考えた。今思い出すと顔が赤くなる論文を書いた。当時、研究結果をまとめると、まず所内研究会で沼知先生臨席の下で発表し、学会発表後高速力学研究所報告に投稿する決まりだった。沼知先生は蔵前高専のご出身で化学を専攻したので、化学の素養をお持ちで、発表に対して「これはよく考えた事例か。アセトンとハロゲン元素気体は猛毒物質を作ることを知っているのか。」の質問、答えに窮していると「非水溶液研究所の所長に話をしておくから、専門家の話を聞くように。」と助言して下さった。やがてこの研究所の旗野昌弘教授から連絡があって、伺うと便覧を開いて「臭素とアセトンでなくて良かったですね、ホスゲンができますよ。」とのことに驚いた。このパラメーターの組み合わせで実験をする予定は全くなかったが、深く物理や化学を考えることなく、思いつきで不出来な論文を書いたことを反省した。
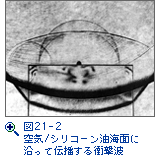 1973年、京都大学の神元五郎教授が第10回国際衝撃波管シンポジューム(The 10th International Shock Tube Symposium)を京都で開催する国際衝撃波管シンポジューム諮問委員会の賛同を得るために、日本の衝撃波研究会を組織することになった。日本衝撃波研究会には本田教授が率いる高速力学研究所の衝撃波管研究も参加して、反射型衝撃波風洞作動の素過程を研究課題に登録した。一方、液体中の衝撃波も研究課題だった。30mm×40mm断面の衝撃波管に直径300mmの測定部を接続し、半円筒形の底にシリコーン油を満たした。空気中でマッハ数3の衝撃波は音速980m/sのシリコーン油の音速を超えて伝わるので、その中を伝播する非常に弱い衝撃波の影写真を撮った。図21-2に示すように、シリコーン油中を伝播する斜め衝撃波は曲面で反射し、反射した圧縮波の包絡線が焦線を作っている。これは光束が曲面で反射して火線ができる現象と同じ物理で、要するにシリコーン油の中で見た波の集積は火線で、液中衝撃波は限りなく線形波に近かった。
1973年、京都大学の神元五郎教授が第10回国際衝撃波管シンポジューム(The 10th International Shock Tube Symposium)を京都で開催する国際衝撃波管シンポジューム諮問委員会の賛同を得るために、日本の衝撃波研究会を組織することになった。日本衝撃波研究会には本田教授が率いる高速力学研究所の衝撃波管研究も参加して、反射型衝撃波風洞作動の素過程を研究課題に登録した。一方、液体中の衝撃波も研究課題だった。30mm×40mm断面の衝撃波管に直径300mmの測定部を接続し、半円筒形の底にシリコーン油を満たした。空気中でマッハ数3の衝撃波は音速980m/sのシリコーン油の音速を超えて伝わるので、その中を伝播する非常に弱い衝撃波の影写真を撮った。図21-2に示すように、シリコーン油中を伝播する斜め衝撃波は曲面で反射し、反射した圧縮波の包絡線が焦線を作っている。これは光束が曲面で反射して火線ができる現象と同じ物理で、要するにシリコーン油の中で見た波の集積は火線で、液中衝撃波は限りなく線形波に近かった。
|



