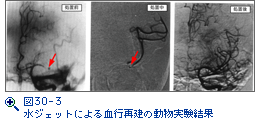衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第4回:衝撃波の医療応用
2006/08
30. 脳血栓血行再建術
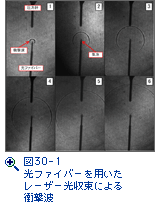 1996年、衝撃波と気泡の干渉を制御する生体軟組織損傷の医療応用を思い付いた。医学部脳神経外科教室との共同で脳血栓の血行再建術にこれを応用する研究を開始した。最初、国立仙台病院の上之原博士と吉本高志教授の積極的な支援を得て、人為的に作った血栓に気泡を貼り付けて、微小爆発で作った衝撃波を照射して、気泡が血栓中に貫入する様子を詳細に可視化した。基礎実験は成功裡に進行したが臨床を視野に入れると、いかに安全と信じても微小爆薬を脳血管の中に入れて起爆するには、医学者ばかりでなく我々も躊躇いを感じた。同様に、脳は水で満たされたコンピュータと等価だから、その中での高圧放電など想像できない。
1996年、衝撃波と気泡の干渉を制御する生体軟組織損傷の医療応用を思い付いた。医学部脳神経外科教室との共同で脳血栓の血行再建術にこれを応用する研究を開始した。最初、国立仙台病院の上之原博士と吉本高志教授の積極的な支援を得て、人為的に作った血栓に気泡を貼り付けて、微小爆発で作った衝撃波を照射して、気泡が血栓中に貫入する様子を詳細に可視化した。基礎実験は成功裡に進行したが臨床を視野に入れると、いかに安全と信じても微小爆薬を脳血管の中に入れて起爆するには、医学者ばかりでなく我々も躊躇いを感じた。同様に、脳は水で満たされたコンピュータと等価だから、その中での高圧放電など想像できない。
ESWL開発史で、1985年、ワシントン大学航空宇宙工学科、ラッセル教授は半切回転楕円体の第一焦点でパルスレーザー光を収束させ球状衝撃波を発生して、これを反射して結石を破砕することを提案した。しかし、パルスレーザー光を正確に第一焦点に収束できないことなどの理由でこのプロジェクトは発展しなかった。
模索の間に、この研究を思い出し衝撃波発生源をレーザーに置き換え、コアー直径0.6mmの先端を凸レンズ形状に成形した石英光ファイバーを通して、波長1.1μm、エネルギー160mJのパルスNd:YAGレーザー光を、水中で収束させた。瞬間的なエネルギーの集積で、水はプラズマとなり爆発的に水蒸気泡を作り、これが球状に膨張するピストンとなって衝撃波を駆動する。図30-1はその衝撃波発生を示す。衝撃波は指向性を持ち、レーザー照射方向に強く、光ファイバー方向には水中音速で、また、光ファイバーに沿っては石英ガラスの音速で伝播する縦波水中に放出された音波が認められる。
 レーザー光の照射方向に伝播する衝撃波は気泡を崩壊する過剰圧を示し、その崩壊で発生する水ジェットは模擬血栓中に貫入する。また、光ファイバーを直接血栓に接触させてレーザー光照射させても血栓は鑽孔された(図30-2)。レーザー光は波長によって水のエネルギー吸収率が異なるので、Nd:YAGレーザーよりも吸収率が飛躍的に大きな波長2.1μm、 エネルギー140mJ のHo:YAGレーザーを用いた。
レーザー光の照射方向に伝播する衝撃波は気泡を崩壊する過剰圧を示し、その崩壊で発生する水ジェットは模擬血栓中に貫入する。また、光ファイバーを直接血栓に接触させてレーザー光照射させても血栓は鑽孔された(図30-2)。レーザー光は波長によって水のエネルギー吸収率が異なるので、Nd:YAGレーザーよりも吸収率が飛躍的に大きな波長2.1μm、 エネルギー140mJ のHo:YAGレーザーを用いた。
直径2mm程度の管末端近くに光ファイバーを挿入してパルスHo:YAGレーザー光を3Hzで照射させたとき爆発的に発生する気泡は管内の水を排除して管出口から間欠的に20m/sの水ジェットを噴出させた。管の先端をやや細くして長さ10mm程度の人工血栓に作用させ、50秒、150回の衝撃波照射で血栓は貫通され除去された。
図30-3は血栓で梗塞した豚の動脈に挿入した水ジェットカテーテルを作用させ血栓除去を試みた処置前から処置後のX線撮影と血流測定結果である。処置後の様子は明らかに血行再建を示している。知見する限り、他の方法に比べ、この方法は処置時間も短く血栓溶解剤などを使わないので脳や臓器の出血の危険は最小である。また、破砕された微細血栓片はカテーテルに同軸状に組み込んだ吸引装置で飛び散ることなく回収され、動物実験は成功した。しかし、この装置を臨床治療に用いるために、安全性の検討など実用を目指す検証が必要で、現在、準備が進行中である。
|