CAEと品質工学寄稿 芝野 広志 氏 高木 俊雄 氏 平野 雅康 氏
実践編:CAEと品質工学を融合した事例
2005/08/24
3. ポイント1:シミュレートする特性値
―基本機能、開発スピードの検討―
基礎編で述べたポイント1を思い出してほしい。品質工学では実験に用いる特性値が最も重要であることを説明した。『品質特性ではなく、基本機能を用いる』である。特性値が実物の計測値でなくCAEを使った場合もこの考え方は変わらない。始めに何を測る(シミュレートする)かをしっかり見極めなければならない。
そこで、紙送り技術を評価するために何を測る(シミュレートする)か検討した結果が図1、2に示す2つの案である。
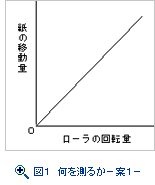 |
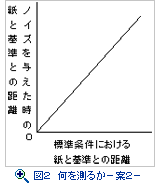 |
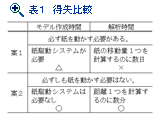 これら2つの案のいずれを採用するか決めるために得失比較を行った。その内容を表1に示す。この得失比較結果から、スピードを重視して、案2を採用する事にした。
これら2つの案のいずれを採用するか決めるために得失比較を行った。その内容を表1に示す。この得失比較結果から、スピードを重視して、案2を採用する事にした。
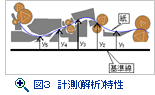 案2であれば紙が静止した状態での解析で良いため、2次元線形静解析を行い、図3に示す基準線との距離yを計測した。
案2であれば紙が静止した状態での解析で良いため、2次元線形静解析を行い、図3に示す基準線との距離yを計測した。
基礎編で、品質工学の目的が『無駄な仕事をさせないこと』であると述べた。無駄な仕事をさせないためには、検討結果を早く出さねばならない。ダメだという結果が遅く出れば出るほど、それまでの無駄な仕事が増えるのである。よって測るスピードはとても重要なのである。
| <1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19> |



