アンテナの歴史と未来
寄稿 安達 三郎 氏
第2回:萌芽
4. 長中波無線通信の発達
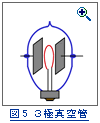
マルコーニの無線装置では、はじめ火花放電を用いていたから混信が原理的にどうしても避けられなかった。特定の周波数に共振するLC回路の原理をロッジが考案(1898年)したことの意義は大きかった。火花放電はやがてアーク放電、ついで高周波発電機にとって代えられた。また、コヒーラは鉱石検波器が発明されて(1906年)その後廃れてしまった。同年、ド・フォーレは3極真空管(図5)を発明した。しかしこれが発振器のみならず増幅器、変調器として多用されるまでには、真空技術が発達するかなりの年数を待たなければならなかった。
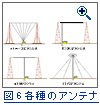
ヘルツの電磁波検証実験では波長が66cm~24cmで行われ、その後数cmのマイクロ波帯で実験を行う者もいたが、電波の利用面では通達距離の有利さから船舶通信や大陸間などの海外通信に適した長波帯通信へと向かった。1912年のタイタニック号の遭難事故を教訓として船舶には無線機の装備が義務づけられるようになった。船舶用のアンテナとしては、ハープ形、逆L形、T形などのトップローデッドアンテナ(図6)が多用された。海外通信用アンテナにはこれらのトップローデッドアンテナや、以下に述べる傘形アンテナなどが用いられた。
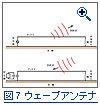
アンテナを高くする代りに、図7に示すように、地表面に沿って張った数kmもの長い導線からなるウェーブアンテナ(ビバレージアンテナ)も用いられた。アンテナ導線の末端は600オーム程度の抵抗を通して接地している。導線にはほぼ進行波が流れるために、電波は地表に沿って前方方向に指向性を持って放射される。受信の場合は逆に前方方向からの電波が左端の受信機で受信される。
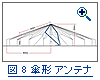
日本では、福島県原町市に対アメリカ向け電信のための長波(20kHz)傘形アンテナ(図8)が立てられた(1920年)。そのための中央コンクリート電波塔の高さは200mであった。アンテナ頂部からは長さ300mのアンテナ線が傘状に54本、放射線状に展張されていた。
長波は遠距離通信用として多用されたが、次に述べるようにこれは次第に短波帯にその席を譲ることとなった。唯一現在でも用いられるものとしては、長波の持つ安定した伝搬特性を利用した電波時計のための標準電波である、特に最近では腕時計用の電波時計さえ現れはじめている。福島県に設置された標準電波は周波数が40kHz(波長7.5km)である。腕時計に内蔵されたアンテナの長さは1.6cmと極めて小さい。波長の約50万分の1である。極超超小形アンテナと言ってよい。1920年以降中波帯の電波はラジオ放送用として多用されるようになった。現在でも円環状のトップロードを持つ垂直アンテナがしばしば使われている。
| <1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18> |



