アンテナの歴史と未来
寄稿 安達 三郎 氏
第1回:黎明
3. マルコーニの通信実験とアンテナ
マルコーニ(写真3)はロッジの発明になる電波検知器、コヒーラ(図3-1,図3-2)を用いて電信通信の実験を行った(1895年)。彼は通信距離を伸ばすためにアンテナを地上高く立ち上げて火花放電端子の1端に接続し、もう1端は大地にアースした。アンテナを高くすることにより共振周波数は低くなるために大地は良導体となり、さらにアースを用いることにより電波は効率よく放射され、かつ大地に沿って遠方まで到達し易くなる。アースすることはアンテナの下半分を大地で代用していると考えることができる。 こうして1899年にはドーバー海峡横断通信に成功し、1901年にはついに大西洋横断通信に成功した。マルコーニはまた、アンテナ頂部の電気容量を大きくするようにアンテナ構造を工夫し、アンテナの実効高を大きくして通信距離を稼いだ。これはアンテナのトップローデイング(図4)と言い、現在でも中波放送用のアンテナや短波帯のアンテナに生かされている。 大西洋横断通信についてケネリーとヘビサイドはその伝搬機構に疑問を持ち、それを説明するために大気超高層には電離層が存在すると予言し(1902年)それによって電波が反射されて長距離を伝搬できると考えた。 ひるがえって日本では、長岡半太郎がヘルツの実験を知るやいち早く追試実験をはじめた(1889年)。松代と木村はマルコーニの無線電信機を独自に開発し、1901年には陸と船の間で130kmの通信に成功している。これらの技術は1901年日本海海戦において信濃丸から「敵艦見ゆ」の無線電信を発信し日本を勝利に導いたとされる。これは無線通信が戦争に用いられた最初の出来事であったと伝えられている。 |
 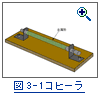 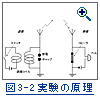 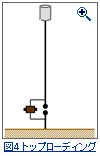 |
| <1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18> |



