建設系エンジニアのための地下構造物三次元FEM事始め伊藤忠テクノソリューションズ(株) 野口 利雄
第1講 ボックス地中構造物の3次元設計アプローチ
二次元解析と三次元解析の対比(配筋)(Step6)
はじめに
ここでは、Step5で示した以下の解析ケースで求めた断面力を用いて許容応力度法による常時の設計を行いました。
| (1)ケース2D | 二次元解析/荷重;通常荷重 | |
| (2)ケース2D3D | 二次元解析/荷重;二方向スラブ荷重 | |
| (3)ケース3D | 三次元解析 |
設計条件
ここでは主鉄筋のみの概略設計としますので、設計時の条件は以下の2つです。
●主鉄筋をD16以上とする。
●鉄筋の芯被りを100mmとする。
なお、隅角部はハンチ端部の値で設計します。
設計結果
図1~5に各ケースの配筋を示します。( )内の数字は断面算から算出された値で、実際の配筋は最小主鉄筋径の条件を考慮の上、決定しています。
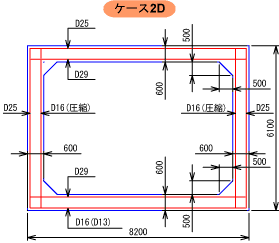 |
図1 |
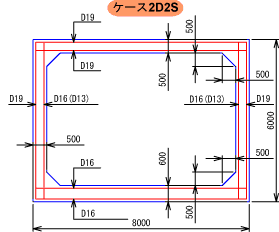 |
図2 |
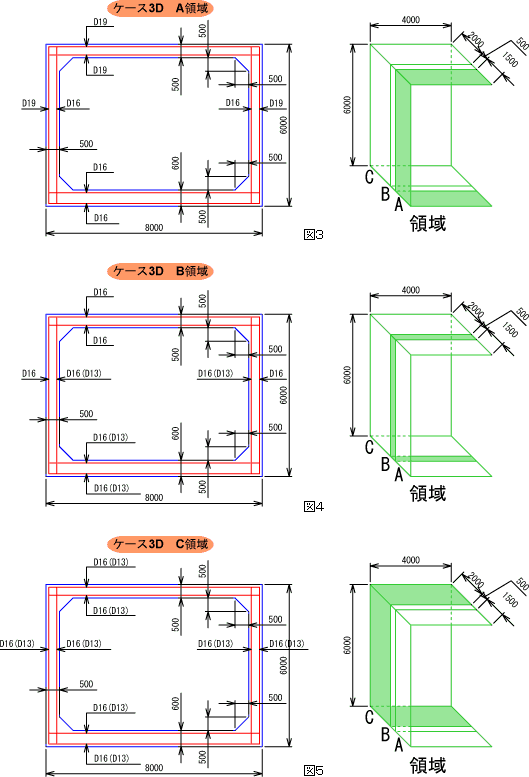 |
|
考察
それらの結果から以下の事柄が言えます。
- ケース2Dは鉄筋だけでなく部材厚も増加する結果になっています。
- ケース2D2Sとケース3DのA領域の結果は等しくなっています。これはケース2D2Sとケース3Dの中央断面で断面力がほぼ等しいのに対応しています。
- ケース3Dは断面力の変化に伴い3種類の配筋領域が設定されます。ただしB領域とC領域は最小主鉄筋径の条件から結果としては等しくなっています。
三次元設計は二次元設計と比較して、コンクリート、鉄筋とも削減が可能となることを示すことができました。今回の例はやや小規模な構造物だったので、その削減効果が十分には発揮できなかった面がありますが、大規模な構造物ではより劇的な差が生ずる可能性は十分にあると言えます。二次元での設計が本当に妥当なのだろうか?という疑問が少しでも頭をかすめたら、三次元での検討を行う価値が十分にあるでしょう。
| | Step1 | Step2 | Step3 | Step4 | Step5 | Step6 | |



