衝撃波の科学寄稿 高山 和喜 氏
第5回:衝撃波と地球惑星物理とのつながり
2006/10
35. マグマ水蒸気爆発
 1991年、雲仙普賢岳が大規模噴火した。地下から押し出された高粘度の溶岩は、火口丘、溶岩ドームを形成した。溶岩ドームは日々高さを増し、重さに耐えられず崩れ落ちて火砕流を作り、火口から有明海の海岸まで農地と人家は荒廃した。6月19日、警戒が一瞬ゆるんだので、外国からの研究者を含む調査団が危険区域の廃墟に立ち入ったとき大規模な火砕流が起こり、逃げ遅れた外国人研究者を含む45人が死亡した。1792年(寛政4年)にも同じような噴火が起こり、火砕流は有明海に流れ込んで大津波を起こし、死者15,000人という有史以来の我国最大の噴火災害が記録されている。
1991年、雲仙普賢岳が大規模噴火した。地下から押し出された高粘度の溶岩は、火口丘、溶岩ドームを形成した。溶岩ドームは日々高さを増し、重さに耐えられず崩れ落ちて火砕流を作り、火口から有明海の海岸まで農地と人家は荒廃した。6月19日、警戒が一瞬ゆるんだので、外国からの研究者を含む調査団が危険区域の廃墟に立ち入ったとき大規模な火砕流が起こり、逃げ遅れた外国人研究者を含む45人が死亡した。1792年(寛政4年)にも同じような噴火が起こり、火砕流は有明海に流れ込んで大津波を起こし、死者15,000人という有史以来の我国最大の噴火災害が記録されている。
1991年7月、仙台で第18回国際衝撃波シンポジウムが開催された。これは衝撃波学際研究に注目した会議だったので、カリフォルニア工科大学スターテヴァント教授に火山噴火に現れる衝撃波現象について招待講演していただくことになった。同教授はシンポジウムの一週間前に来日して磐梯山を訪れた。招待講演の話題の一部は1883年磐梯山噴火を衝撃波工学の立場から解釈する内容だった。講演論文の共著者は雲仙普賢岳噴火調査で来日していたアメリカ地質研究所のグリッケン博士で、雲仙普賢岳の火砕流の犠牲者の一人だった。講演に先立ってグリッケン博士の死を悼む、異例の招待講演となった。まず、1883年、磐梯山大噴火と1981年アメリカ・セントヘレンの大噴火では、火砕流が火山災害の原因となったこと、二つの火山噴火の駆動力は地下のマグマ水蒸気爆発で、爆発的噴火と衝撃波現象は重要なつながりを持っていることを詳細に解説し、さらに同教授が行っているマグマの微細化の模擬実験と力学モデルが紹介された。
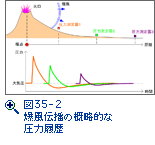 6月19日の普賢岳噴火は爆発的で爆風伝播を伴った。爆発に伴う衝撃波は一般に爆風と呼ばれている。爆風波面は急峻な圧力上昇を伴い、高圧は直ちに減少して、大気圧をやや下回る値に達し、その後大気圧に回復する(図35-2)。そのとき火山学者は、噴火の爆風圧を計測するために、普賢岳の近傍に爆風計(blast gauge)を配置した。これは爆風に対面させた直径50~60mmの薄い鉛板からできていて、爆風があたって鉛板の変形くぼみの深さから力積を推定し、最高圧を求めようとする簡便計測である。6月19日の爆風を火口から2km離れたくぬぎ平で、記録に成功した。この爆風計の鉛板変形を、衝撃波管を使った実験で校正できないかという依頼を受けた。
6月19日の普賢岳噴火は爆発的で爆風伝播を伴った。爆発に伴う衝撃波は一般に爆風と呼ばれている。爆風波面は急峻な圧力上昇を伴い、高圧は直ちに減少して、大気圧をやや下回る値に達し、その後大気圧に回復する(図35-2)。そのとき火山学者は、噴火の爆風圧を計測するために、普賢岳の近傍に爆風計(blast gauge)を配置した。これは爆風に対面させた直径50~60mmの薄い鉛板からできていて、爆風があたって鉛板の変形くぼみの深さから力積を推定し、最高圧を求めようとする簡便計測である。6月19日の爆風を火口から2km離れたくぬぎ平で、記録に成功した。この爆風計の鉛板変形を、衝撃波管を使った実験で校正できないかという依頼を受けた。
そこで、爆風計を直径230mm衝撃波管の開口部直後に対面して取り付け、マッハ数が分かっている衝撃波を爆風計の鉛板に作用させ、できた鉛板の凹みと噴火爆風を記録したくぼみを比較した。同じ深さのくぼみを作った衝撃波のマッハ数を噴火の爆風のマッハ数と仮定した。その結果、爆風計が検知した爆風のマッハ数は約1.2だった。力積は2トントラックが時速40kmで衝突した場合に相当し、非常に強い爆風が発生したことになる。
圧電型圧力変換器や光ファイバー圧力変換器で衝撃波の過剰圧を測るのは、衝撃波実験では基本であるが、野外計測を行う火山学では、伝統的に鉛板の爆風計のような簡便であるが精度が保証されていない計測が行われているのに驚いた。
|



