地下構造物三次元FEM設計
円形開口部
はじめに
ここでは、設計サンプルとしてシールド発進立坑のような円形開口部がある構造物を題材に取り上げ、二次元設計と、三次元設計の比較検討を行います。想定した構造物は、幅15m、高さ10mの壁に直径8mの円形開口部があります。従来の二次元設計と三次元設計で配筋決定を行い、双方のアプローチでの違いを比較します。
設計緒元と設計条件
図1に設計対象の構造物、土質条件、土圧を示します。
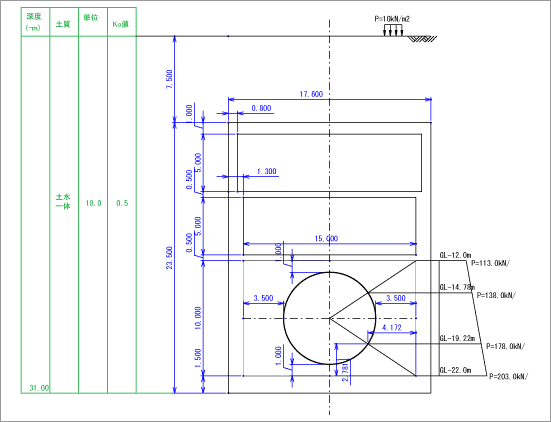 図1 設計対象の構造物、土質条件、土圧
図1 設計対象の構造物、土質条件、土圧
二次元設計法では、図2のように鉛直方向と水平方向をそれぞれ分布荷重が作用する片持ち梁として計算し設計します。対する三次元設計では、図3のように構造物の形状及び荷重を忠実にモデル化し、土圧を作用させます。
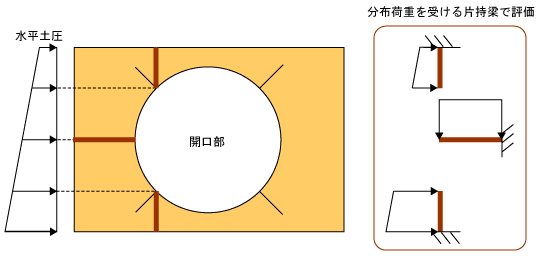 図2 二次元設計法
図2 二次元設計法
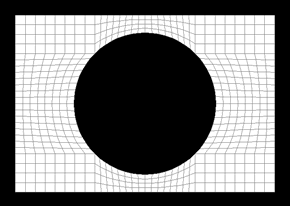
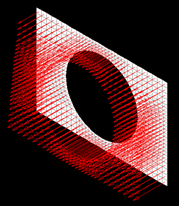 図3 三次元設計モデルと荷重条件
図3 三次元設計モデルと荷重条件構造解析結果│
図4~図6に三次元解析結果を示します。
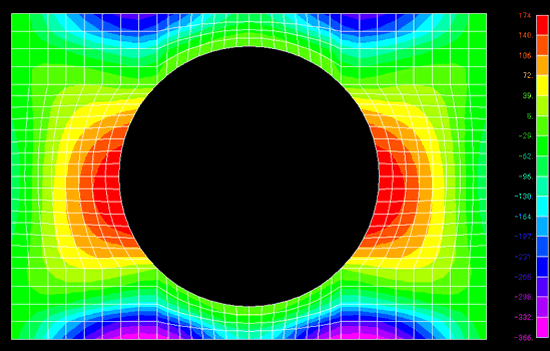 図4 三次元解析結果;水平軸回り曲げモーメント
図4 三次元解析結果;水平軸回り曲げモーメント
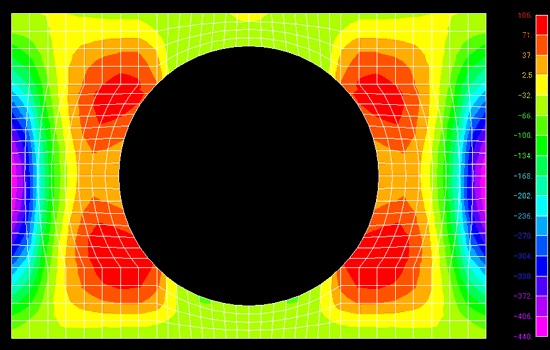 図5 三次元解析結果;鉛直軸回り曲げモーメント
図5 三次元解析結果;鉛直軸回り曲げモーメント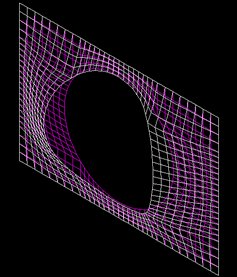 図6 変形図
図6 変形図配筋結果│
表1に二次元、三次元解析結果から求めた部材断面力及び鉄筋量の一覧を示します。また、図7に二次元設計、三次元設計それぞれの配筋例を示します。
■ 断面力
| |
部材長(m) |
p1(固定端) |
p2(自由端) |
2D_M |
3D_M |
3D/2D比 |
| 鉛直方向上部 |
2.78 |
113.00 |
138.00 |
598.09 |
287.90 |
0.48 |
| 鉛直方向下部 |
2.78 |
203.00 |
178.00 |
720.55 |
366.50 |
0.51 |
| 水平方向 |
3.50 |
178.00 |
178.00 |
1090.25 |
441.20 |
0.40 |
|
■ 鉄筋量
| 表1 二次元設計/三次元設計部材断面力及び鉄筋量一覧 |
| |
|
二次元 |
三次元 |
| ケース名 |
|
鉛直方向上部 |
鉛直方向下部 |
水平方向 |
鉛直方向上部 |
鉛直方向下部 |
水平
方向 |
鉛直方向2 |
水平方向2 |
| B |
(cm) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| H |
(cm) |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
| M |
(tf・m) |
59.8 |
72.1 |
109.0 |
28.8 |
36.7 |
44.1 |
24.5 |
19.2 |
| N |
(tf) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| n=Es/Ec |
|
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
| σca |
(kgf/cm2) |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
| σsa |
(kgf/cm2) |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
1800 |
| d1 |
(cm) |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
115 |
| 本数-鉄筋 |
|
8-D25 |
8-D25 |
8-D32 |
8-D19 |
8-D19 |
8-D22 |
4-D22 |
4-D22 |
| As1 |
(cm2/100cm) |
40.54 |
40.54 |
63.54 |
22.92 |
22.92 |
30.97 |
15.48 |
15.48 |
| x |
(cm) |
31.8 |
31.8 |
38.2 |
24.9 |
24.9 |
28.4 |
20.9 |
20.9 |
| σc' |
(kgf/cm2) |
36.0 |
43.4 |
55.7 |
21.7 |
27.6 |
29.5 |
21.7 |
21.2 |
| σc |
(kgf/cm2) |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| σs1 |
(kgf/cm2) |
1413.1 |
1703.7 |
1677.8 |
1177.6 |
1500.6 |
1349.3 |
1464.7 |
1428.8 |
| 長さ |
(cm) |
1000.0 |
|
1500.0 |
1000.0 |
|
1500.0 |
1000.0 |
1500.0 |
| 分担幅 |
(cm) |
1500.0 |
|
1000.0 |
1100.0 |
|
600.0 |
400.0 |
400.0 |
| 面積 |
(cm2) |
1500000.0 |
|
1500000.0 |
1100000.0 |
|
900000.0 |
400000.0 |
600000.0 |
| 円形補正 |
(cm2) |
528102.0 |
|
528102.0 |
528102.0 |
|
432152.0 |
0.0 |
95950.0 |
| 補正後面積 |
(cm2) |
971898.0 |
|
971898.0 |
571898.0 |
|
467848.0 |
400000.0 |
504050.0 |
| 鉄筋体積 |
(m3) |
0.394 |
|
0.618 |
0.131 |
|
0.145 |
0.062 |
0.078 |
| 圧縮鉄筋 |
(m3) |
0.131 |
|
0.206 |
0.044 |
|
0.072 |
0.021 |
0.039 |
| 計 |
(m3) |
|
|
1.349 |
|
|
|
|
0.592 |
| 3D/2D比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.44 |
|
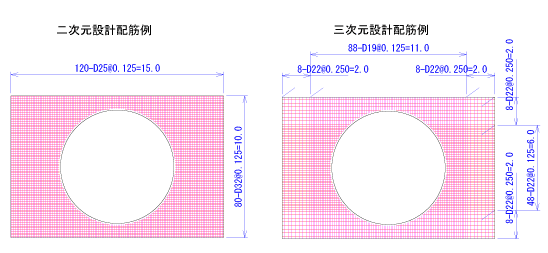 図7 二次元設計/三次元設計配筋例
図7 二次元設計/三次元設計配筋例考察│
二次元設計では、鉛直方向と水平方向を独立に片持ち梁でモデル化したことに対し、三次元設計では開口部部材が一体で評価でき、実現象に近い断面力分布が得られていると考えられます。そのため三次元設計による配筋は部材周辺部の鉄筋量が低減でき、二次元設計の約半分程度となりました。今回の例は開口部水平方向の離れがやや大きいですが、円形開口部は三次元設計が有効な箇所と考えられます。

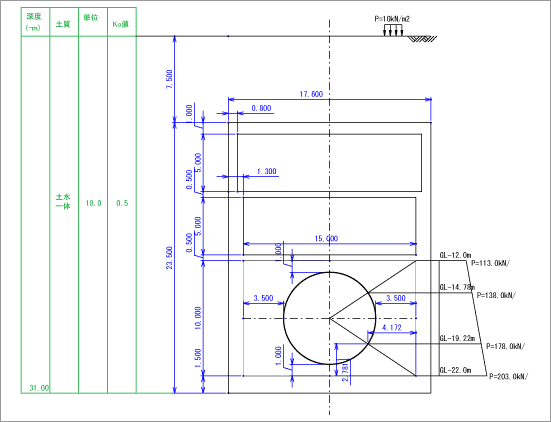 図1 設計対象の構造物、土質条件、土圧
図1 設計対象の構造物、土質条件、土圧 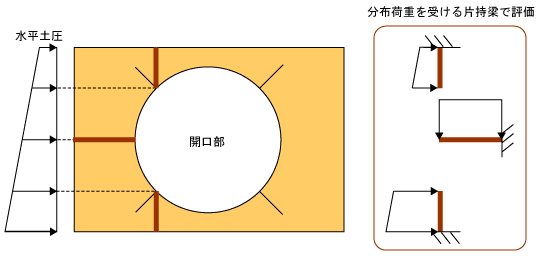 図2 二次元設計法
図2 二次元設計法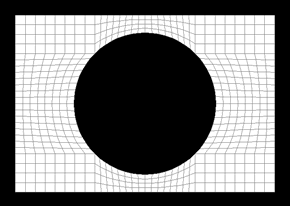
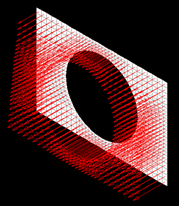 図3 三次元設計モデルと荷重条件
図3 三次元設計モデルと荷重条件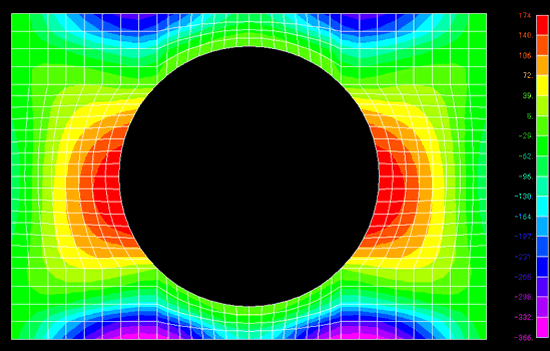 図4 三次元解析結果;水平軸回り曲げモーメント
図4 三次元解析結果;水平軸回り曲げモーメント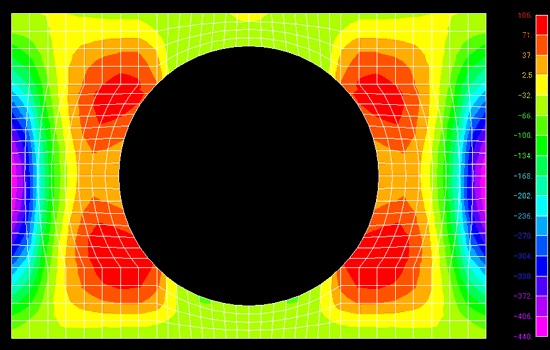 図5 三次元解析結果;鉛直軸回り曲げモーメント
図5 三次元解析結果;鉛直軸回り曲げモーメント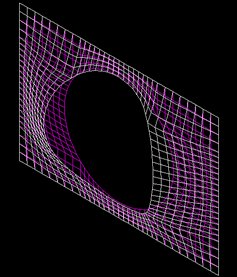 図6 変形図
図6 変形図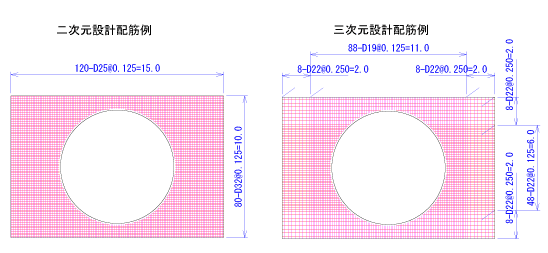 図7 二次元設計/三次元設計配筋例
図7 二次元設計/三次元設計配筋例


