性能照査型設計法に基づく橋梁設計の基礎知識と応用山梨大学大学院 医学工学総合研究部 環境社会創生工学専攻 杉山 俊幸 教授
講座概要
土木構造物や建築構造物のような構造物が保有する性能、すなわち、さまざまな荷重作用下での構造物の挙動は,必ずしも明確ではない。これは、
- 従来の設計体系では、決められた手順をたどる設計を行えばよく、設計者は自身が設計した構造物の性能を必ずしも把握していないこと
- 構造物の性能は大きな外力が作用した時に初めて明らかになることが多いが、発生が稀な外力の特性や大きな外力作用時の構造物の挙動の予測は容易でないこと
- 既存の構造物の大半は際立った支障が生ずることなく供用に耐えてきており、ある程度の安全性等が現行の設計規準で確保されていると考えられること
- 一般市民の間には構造物が安全であることは当然との認識があり、コストと構造物の保有する性能とのバランスが必ずしも認識されていないこと
等の理由により、構造物の性能を明確に評価するための技術が体系的に確立されてこなかったことが原因と考えられよう。設計体系のあるべき本来の姿としては、設計者が自身の設計した構造物の性能を十分に把握し、構造物の性能に関する情報を利用者に提供することで、構造物の保有する性能が価値判断の材料となることであると言えよう。こうした技術的側面からみた設計規準の欠点を克服するための1つの方法として導入がなされてきているのが性能照査型設計である。我が国では、建築分野・土木分野ともに性能照査型設計導入のための活動が積極的になされている。本Webセミナーは、今後ますます定着化の方向にある性能照査型設計について、特に橋梁設計に関しての基礎知識と応用を論じ、読者の理解を深めるための一助としたい。
ダウンロード
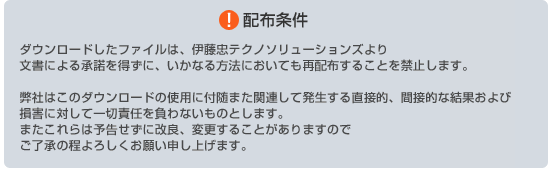
| 第1章 序論 | ||
|---|---|---|
| 第2講 橋に要求される性能と設計段階で考慮される限界状態 | ||
| 第3講 性能照査型設計法に基づく橋の断面決定 | ||
目次
| 第1章 序論 [公開中] | |
|---|---|
| 1.1 性能照査型設計導入の背景 1.2 性能照査型設計導入の経緯 1.3 性能照査型設計の長所と課題および性能照査型 設計のフロー 1.4 用語の定義 |
|
| 第2章 橋に要求される性能と設計段階で考慮される限界状態 [公開中] | |
| 2.1 橋に要求される性能 2.2 設計段階で考慮される限界状態 2.3 設計時に目標とする性能レベルの設定 |
|
| 第3講 性能照査型設計法に基づく橋の断面決定 [公開中] | |
| 3.1 荷重作用の設計値の設定 3.2 構造材料強度の設計値の設定 3.3 構造解析手法、耐荷力解析手法の選定 3.4 応答値と限界値の算定 3.5 設計終了段階での保有性能の評価 3.5.1 性能照査フォーマット 3.5.2 許容応力度設計方式の欠点と部分安全係数設計方式の利点 3.5.3 信頼性理論に基づく照査方法 |
|
| 第4講 施工段階・供用期間中における性能の照査と補修・補強 | |
| 4.1 施工の良否と完成後の保有性能 4.2 施工終了時の性能の照査 4.3 供用期間中における性能の照査 4.4 補修・補強 |
|
| 第5講 限界状態到達へのシナリオと限界状態に到達した場合の対応 | |
| 5.1 限界状態到達へのシナリオ 5.2 限界状態に到達した場合の対応 |
|
| 第6講 性能照査型設計法導入に必要な社会体制 | |
| 6.1 技術基準体系 6.2 審査・認定制度 6.3 入札・契約方式 6.4 リスク管理と保険の導入 |
|



