今月号は、「超音波ソリューションセミナーFY2024」、「マテリアルDXセミナー2024」、「LS-DYNA ユーザーカンファレンス 2024」の開催報告を紹介いたします。ぜひご覧ください。
皆様のご意見、お待ちしております。以下のリンクからぜひアンケートにお答えください!
2024年10月31日 編集委員
トランスシミュレーションでは、「事業や産業の領域を超えて、データを掛け合わせる」、「AI、シミュレーション、IoTなど、テクノロジーのジャンルにとらわれずに組み合わせる」など、目的や課題に合わせて、より自由なカタチで最適解を目指すのが「トランスシミュレーション」です。
弊社では、随時Trans Simulation最新事例をご紹介していきます。
スマートマニュファクチャリング構築ガイドラインによるデジタル化
経済産業省が策定した『スマートマニュファクチュアリング構築ガイドライン』において、デジタルツインは製造業のデジタルトランスフォーメーションを加速させる重要な要素として位置づけられています。
本稿では、同ガイドラインを踏まえ、デジタルツインの概念とその製造現場における具体的な活用事例を紹介するとともに、多頻度データ収集やシミュレーションによる最適化など、ガイドラインで提唱される高度なデジタル化の実現に向けたCTCの取り組みを詳細に解説いたします。・・・

詳細はこちら!
https://x-simulation.jp/blog/91
多品種小ロット生産の課題解決!業界別事例をご紹介
多品種小ロット生産は、多様な顧客ニーズに応えるために、多くの品種を少量ずつ製造する生産方式です。近年、多くの企業がこの生産方式を採用していますが、同時に多くの課題にも直面しています。本記事では、多品種小ロット生産におけるこれらの課題と、シミュレーションによるその具体的な解決策について業界別に詳しく紹介します。・・・

詳細はこちら!
https://x-simulation.jp/blog/83
製造業界BIM:Boxとクラウドを連携した3Dビューアによる生産性向上
製造業において、3Dビューアやクラウド技術はますます重要な役割を担っています。これらのツールは、設計から製造、品質管理までのさまざまなプロセスで活用され、効率性と精度を向上させるための強力な手段となっています。
本記事では、3Dビューアとクラウド技術の具体的な役割とその利点について詳しく説明します。・・・

詳細はこちら!
https://x-simulation.jp/blog/86
CCS事業法の概要と用語紹介!脱炭素化が難しい分野のGXを目指す
2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、今後、脱炭素化が難しい分野におけるGXを実現することが課題となっております。このような分野における化石燃料・原料の利用後の脱炭素化を進める手段として、CCSの導入が不可欠です。
そこで今回は、2024年5月に成立した「二酸化炭素の貯留事業に関する法律」(以下CCS事業法)の内容と、よく出てくる用語に関しまして解説・紹介いたします。・・・

詳細はこちら!
https://x-simulation.jp/blog/89
Trans Simulation サイトはこちら
https://x-simulation.jp/
Trans Simulation 最新事例一覧はこちら
https://x-simulation.jp/blog
2024年9月5日、神谷町トラストタワー2Fにて、「【超音波ソリューションセミナーFY2024】~GX、AI、モビリティ、半導体、医療を対象とした各種事例紹介、ComWAVE X新機能リリース、将来展望~」と題しまして、弊社伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の超音波関連プロダクトのユーザー会を開催いたしました。
当日は多くの方にご参加いただき、セミナー、交流会ともに活発な質疑応答/議論が交わされ、大いなる盛り上がりの中、当セミナーを終えることができました。この場を借りて御礼申し上げます。
今回のセミナーでは、愛媛大学 中畑 和之様による基調講演のほか、AI、モビリティ、半導体ユーザー様による事例紹介3件、及び、新しくリリースされたサブスク版「ComWAVE X2024」による最新機能の紹介が行われました。
本稿では、セミナーの様子の一部についてご紹介いたします。・・・

続きはこちら↓
https://www.engineering-eye.com/rpt/column/2024/0905_seminar.html
2024年10月2日(水)に弊社神谷町(本社)オフィスにて、マテリアルDXセミナー「社会課題解決の加速へ向けた合金材料開発」を開催いたしました。当日は遠方の方々含め多くの方にご参加頂きましたこと、御礼申し上げます。
本セミナーでは、マテリアルDX、GX、ICME(Integrated Computational Materials Engineering)、シミュレーションなどをキーワードに、お客様の取り組みやCTC、QuesTek(注1)の最新ソリューション、デジタル材料設計プラットフォームICMDの紹介などを行いました。
(注1)
QuesTekは合金材料開発において高度な技術を有する米国の会社です。
CTCではQuesTek社との合弁事業を推進しています。
https://www.ctc-g.co.jp/company/release/20230921-01628.html
お客様講演として、大同特殊鋼株式会社様からICMD®(QuesTekのSaaSプラットフォームであるデジタル材料設計プラットフォーム)を用いた取り組み事例についてご講演いただきました。また、国立研究開発法人 物質・材料研究機構様からは、材料研究・開発の取り組みをご紹介していただきました。・・・
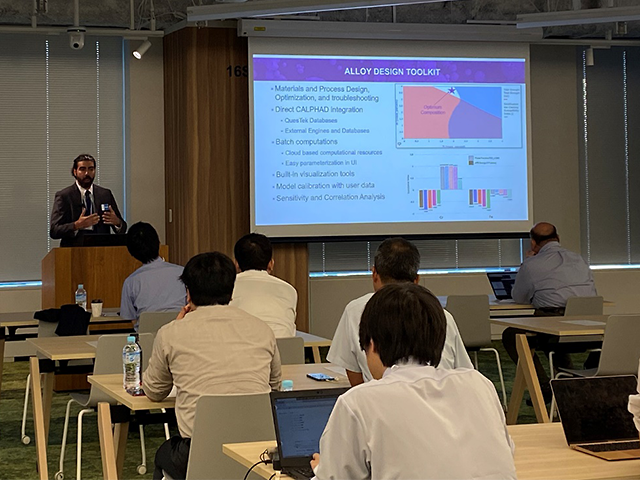
続きはこちら↓
https://www.engineering-eye.com/rpt/column/2024/1002_seminar.html
CTCのLS-DYNAユーザーカンファレンスとしては、約4年ぶりとなるリアルイベント(対面)開催でした。50名以上が参加され、イベント終了後にはささやかな懇親会も開かれました。こちら に講演概要などの情報があります。

今回は基調講演をスズキ株式会社様より賜り、好評を博しました。「スズキにおける衝突CAEの取り組み」と題して行われたこの講演では、海外のモータリゼーション動向やそれに伴う交通事故件数の深刻な伸びに触れた後、交通安全対策の考え方や各国の試験規格など基本的な事柄も含めわかりやすく解説いただきました。それらを踏まえた上で、先進的な解析技術の導入や精度向上への取り組みなどスズキにおける衝突CAEの取り組みが紹介されました。ばらつき評価を解析に取り入れ、設計段階でばらつきの起きにくい構造にリバイズした事例が示され、聴講者に驚きと感銘を与えました。・・・
続きはこちら↓
https://www.engineering-eye.com/rpt/column/2024/1004_seminar.html
2024年10月31日発行
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
エンタープライズ事業グループ 科学システム本部 科学営業第3部
住所:〒105-6950 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー
E-mail:science_info@ctc-g.co.jp
https://www.engineering-eye.com/