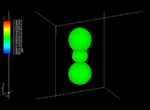アンテナの歴史と未来
寄稿 安達 三郎 氏
第3回:探究
7. 線状アンテナの理論
これまで主にアンテナの実際について述べてきたが、ここで少し理論の歴史について触れてみるのも意味があろうと思う。へルツが初めて電磁波の検証実験に成功して間もなく、ポックリングトンは細い導線に沿って流れる電流は近似的に光の速度で伝搬すること、そして電流は正弦波分布をしていることを理論的に示した(1897年)。これは重要な理論的な発見であった。線状アンテナの理論は始めにそのような電流を仮定し、その電流自体が作る電界に抗して電流が流れるために必要な複素電力からアンテナのインピーダンスを計算する方法が用いられた。 この方法は起電力法と呼ばれていて、現在でも十分に細い線状アンテナの近似的な計算方法として広く便利に用いられている。
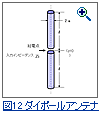 ハレンは、ある有限な太さを持つ有限な長さの円柱アンテナに流れる電流について、それが作る電界がアンテナの表面での境界条件を満たすような積分・微分方程式を導き、導線が十分細いとして逐次近似法による電流分布の漸近展開式を与えた(1938年)。この結果は有限な太さのより現実的な円柱ダイポールアンテナ(図12)の初めての理論として注目された。
ハレンは、ある有限な太さを持つ有限な長さの円柱アンテナに流れる電流について、それが作る電界がアンテナの表面での境界条件を満たすような積分・微分方程式を導き、導線が十分細いとして逐次近似法による電流分布の漸近展開式を与えた(1938年)。この結果は有限な太さのより現実的な円柱ダイポールアンテナ(図12)の初めての理論として注目された。
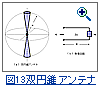 もう一つの重要な理論として、シェルクノッフによる双円錐アンテナの理論がある(1941年~1946年)。これは図13(a)に示すようなアンテナで、アンテナを囲む球の内部領域と外部領域の電磁界をそれぞれの固有球波動関数で展開した後、これらを境界面で接続する。 この理論はアンテナのモード理論とも呼ばれる。 結果的にアンテナの入力インピーダンスは図13(b)に示される等価回路で表されることになる。 ここで、給電点からアンテナの端までは一定の特性インピーダンスZoを持つ伝送線路になっており、その終端に接続されたインピーダンス、Ztはアンテナの終端から外部の放射空間を見たインピーダンスに対応する。 このようにして計算されるインピーダンスの値はハレンの円柱アンテナのそれとは多少の差異が現れる。 有限な太さのアンテナの理論としてはもう一つ、扁長スフェロィダルアンテナの理論(チュウ・ストラットン、1941年)があるが、この場合もアンテナの太さが場所によって変化するために上記の2つの理論結果とも多少異なる。
もう一つの重要な理論として、シェルクノッフによる双円錐アンテナの理論がある(1941年~1946年)。これは図13(a)に示すようなアンテナで、アンテナを囲む球の内部領域と外部領域の電磁界をそれぞれの固有球波動関数で展開した後、これらを境界面で接続する。 この理論はアンテナのモード理論とも呼ばれる。 結果的にアンテナの入力インピーダンスは図13(b)に示される等価回路で表されることになる。 ここで、給電点からアンテナの端までは一定の特性インピーダンスZoを持つ伝送線路になっており、その終端に接続されたインピーダンス、Ztはアンテナの終端から外部の放射空間を見たインピーダンスに対応する。 このようにして計算されるインピーダンスの値はハレンの円柱アンテナのそれとは多少の差異が現れる。 有限な太さのアンテナの理論としてはもう一つ、扁長スフェロィダルアンテナの理論(チュウ・ストラットン、1941年)があるが、この場合もアンテナの太さが場所によって変化するために上記の2つの理論結果とも多少異なる。
以上は、いわば古典的な線状アンテナの理論で、現在では後に述べるようにコンピュータを駆使したより精度の高い数値解析法が開発されている。 しかし、最初に述べた起電力法による理論はその簡便さと解の唯一性によって現在でもその意義を失っていない。